英語でさるく 那須省一のブログ
魚津に遊ぶ
- 2015-04-12 (Sun)
- 総合

大阪、京都を経由して小雨の中、富山・魚津に向っている。JR特急サンダーバード号。魚津は二年ぶりの訪問だ。東京時代にお世話になった親しい知人を訪ねる。東京からも一人友人が合流する。懐かしい面々との再会だから飲まないわけにはいかないだろう。体重増は不可避。まあいい。福岡に戻ったら断酒粗食の日々が待っている。帳尻は合うだろう。
旅の合間に読んでいたヘロドトスの『歴史』(岩波文庫・松平千秋訳)の上巻を読み終えた。前々回の項で紹介した以外で印象に残っている記述を以下に断片的に記しておきたい。
◇
コーカサス山中には多種多様の人種が多数棲息しているが、その大部分はもっぱら野生の木の実などを食糧にして生きている。(中略)これらの人種の男女の交わりは、家畜と同じく公然と行われる。
エジプト人は・・・小便を女は立ってし、男はしゃがんでする。一般に排便は屋内でするが、食事は戸外の路上でする。どうしてもせねばならぬことでも恥ずかしいことは秘かにする必要があるが、恥ずかしくないことは公然とすればよい、というのが彼らの言い分なのである。

南が西に傾いている方角では、エチオピアが人の住む世界の涯になる。この国は多量の金、巨大な象、さまざまな野生の樹木に黒檀を産し、この国の住民は世界中で体躯はもっとも大きく、容姿は最も美しく、寿命は最も長い。
インド人の国土の東方は砂漠を成し、実際われわれの知る限り、またわれわれが多少とも確実な知識をもっている限りにおいて、アジアに住む人類の内ではインド人が最東端の民族なのである。インドの東方は砂漠を成しているため全く無人の境だからである。
西の方ヨーロッパの端の地域については、私は確実な知識をもたない。少なくとも私は、琥珀の原産地と伝えられる、北の海に注ぐ河があって、異国人たちがその河をエリダノスと呼んでいるというごとき話を信ずることはできないし、わが国に渡来する錫の原産地であるというカッシテリデス(「錫島」)の実在することも知らないのである。
◇
古代ギリシアの歴史家ヘロドトス(484BC-430BC)の時代の人々にとって、日本や中国、英国、フランスなどは「存在」しなかったも同然だったのだ。
上巻の中では最後に次の文章を自分の記憶に焼き付けたいと願った。
◇
実際どこの国の人間にでも、世界中の慣習の中から最も良いものを選べといえば、熟慮の末誰もが自国の慣習を選ぶに相違ない。このようにどこの国の人間でも、自国の慣習を格段にすぐれたものと考えているのである。そうだとすれば、これほど大切なものを嘲笑の種にするなどということは、狂人ででもなければ考えられぬ行為といえるであろう。
◇
古代ギリシアの歴史家の「気づき」を二千五百年後の先進文明の現代に住む我々人類は今なお「手本」としなければならない。我々は果たして少しは賢くなったのだろうか?
(写真は上が、魚津の温泉でくつろぐ私。このような写真をお許しあれ! 下はお世話になったMママのご馳走に舌鼓を打つ)
- Comments: 0
徳島の旅
- 2015-04-06 (Mon)
- 総合

徳島の講演会も無事終了し、今、バスで大阪入りして、いつものホテルにチェックインして、ロビーでこのブログを書いているところだ。一年前に「徳島トーストマスターズクラブ」の皆さんと交わした約束を何とか果たしてほっとしている。
今回のイベントは徳島トーストマスターズクラブの結成15周年を祝った行事だった。私が徳島の皆さんにこうやって講演するのは今回が4回目。例によって、講演後、しまった、あの話をするのを忘れた、英語で話す部分が少なすぎたかなどと反省もしたが、心優しいマスターズクラブの方々からは「ご苦労様でした」とねぎらいのことばをかけて頂いた。
私の講演に続いて、クラブの活動内容が一般の人々に紹介された。トーストマスターズクラブでは英語のスピーチ技術アップを目指して、例会で会員が相互にスピーチを披露し、その内容、用語、時間が厳しくチェックされる。英語スピーチの熟練度が試される場であり、一年ぶりに皆さんのスピーチ、及び、その評価などを目に耳にして、改めて彼らの真剣さに打たれた。こうした活動があまり一般には知られていないのは残念なことだ。

これまでは講演会のためだけに徳島入りしてろくに観光らしきものをせず、関西方面に出てきていた。今回はマスターズクラブの会長の田村実さんがご親切にも「駆け足ですが、少し地元をご案内しましょう」と誘って頂いた。足を運んだのは四国八十八か所巡礼の一番札所の霊山寺(りょうぜんじ)。夕刻が迫る時間帯だったが、それでも巡礼の人たちが何人もいて、それなりの雰囲気に浸ることができた。四国四県にまたがる巡礼コースは全長1400キロとか。貴重な観光資源ともなっているのだろう。そういえば、宮崎の古里にも「ひむか神話街道」とかいう看板を見たことがある。四国巡礼の旅のようなものに成長させることはできないものか。

霊山寺の後、鳴門の渦潮を見ましょうということで鳴門に向かった。大鳴門橋の下に遊歩道のような歩道「渦の道」が設けられていて、潮流の運が良ければ、有名な鳴門の渦潮を見ることができるとか。上部をひっきりなしに車が通過する橋の真下の歩道はさすがにうるさかったが、眺めは良かった。大きな渦潮は見ることができなかったが、それでも潮目というか、二つの潮の流れがぶつかる自然の光景は圧巻だった。あの潮目にぶつかったら、泳ぎ抜けるのはまず不可能だろう。
アフリカ特派員時代にケニアかどこかの海で小さな船で沖に出たことがある。泳ぎたくなって、案内の地元の若者に「私でも泳げるだろうか」と尋ねたら、「泳げる」との返事。安心して飛び込んで、泳ごうとしたが、波がきつくて泳ぐどこの話ではない。浮かんでいるだけでも大変だ。振り返って見ると、船ははるか向こうに漂っているではないか。大きな声を張り上げて船上の若者を呼んだ。あの時はひょっとしたら、このまま、自分は体力が尽きて溺れ死ぬのではないかという恐怖感が頭をよぎった。緩やかな滝のような潮の流れを眼下に見ながら、そんなことを思い出してしまった。
泳ぎは下手だが、泳ぐのは好きだ。今回の旅でもできればプールで泳ごうと思ってスイミングパンツにキャップ、ゴーグルは持参している。明日は大阪勤務時代によく通った市民プールに行って泳ぐ(歩く)つもりだ。
(写真は上から、徳島トーストマスターズクラブの創設15周年記念イベントでの記念撮影、四国巡礼一番札所・霊山寺の門前、「潮の道」から眺めた渦潮)
- Comments: 2
ヘロドトスの『歴史』
- 2015-04-02 (Thu)
- 総合
紀元前5世紀に生きたギリシアの歴史家ヘロドトスが著した『歴史』を読んでいる。西アジアを当時席巻していたペルシア帝国がギリシア諸都市の征服を目指して突き進んだペルシア戦争と呼ばれる東西抗争の歴史を綴った書だ。
岩波文庫の全三巻の翻訳『歴史』。古代ギリシア文学者の松平千秋氏(故人)の労作で初版は1971年。私が手にしているのは2013年刊の第52刷というから、長年にわたって読み継がれてきた名著であることがうかがえる。上巻の「はしがき」の冒頭に次のように記されている。———— 本書は、ローマのキケロによって「歴史の父」と称されたヘロドトス(前四八四ごろ——四三〇以後)の著作「歴史」の全訳である。————
ヘロドトス自身は歴史上の偉大な出来事が時の経過とともに忘れ去られることのないように筆を執っているのだと述べ、冒頭に近い部分で「かつて強大であった国の多くが、今や弱小となり、私の時代に強大であった国も、かつては弱小であったからである。されば人間の幸運が決して不動安定したものでない理(ことわ)りを知る私は、大国も小国もひとしく取り上げて述べてゆきたいと思うのである」と記している。
この書の中にふんだんに盛り込まれている説話やその土地々々の時代風習が興味深い。小アジアの異邦人であるリュディア王国のクロイソス王は諸国を歴訪しているアテナイ(アテネ)の賢人に尋ねる。「世界で一番仕合せな人間」に遭遇したことがあるかと。彼は賢人がそれは王様ご自身ですという返答を期待していた。だが、その賢人は次のようにすげなく答える。「どれほど富裕な者であろうとも、万事結構ずくめで一生を終える運に恵まれませぬ限り、その日暮らしの者より幸福であるとは決して申せません。腐るほど金があっても不幸な者も沢山おれば、富はなくとも良き運に恵まれる者もまた沢山おります。(中略)人間死ぬまでは、幸運な人とは呼んでも幸福な人と申すのは差控えねばなりません」
上巻ではナイル川やそこに住むエジプト人のことが詳述されている。「エジプト人はこの国独特の風土と他の河川と性格を異にする河とに相応じたかのごとく、ほとんどあらゆる点で他民族とは正反対の風俗習慣をもつようになった。(中略)小便を女は立ってし、男はしゃがんでする」。アルテミス(ギリシア神話の月と狩りの女神)の祭りに参集するエジプト人の様子は次のように書かれている。「男女一緒に船で出かけるのであるが、どの艀(はしけ)も男女多数が乗り組む。カスタネットを手にもって鳴らす女がいるかと思えば、男の中には船旅の間中笛を吹いているものもある。残りの男女は歌をうたい手を叩いて拍子をとる。船がどこかの町を通る時には、(中略)ほかの女たちは大声でその町の女たちに呼びかけてひやかし、踊るものもあれば、立ち上がって着物をたくしあげる者もある。(中略)この祭で消費する葡萄酒の量は、一年の残りの期間に使う全消費量を上廻るのである」
あれ、この当時はエジプトの宗教的戒律はそれほどでもなかったのか、と思い、すぐに自分の無知に気づいた。これは紀元前5世紀の物語だ。中東世界でイスラム教が誕生したのは西暦7世紀まで待たなければならない。イエス・キリストもまだ誕生していない時代のお話(歴史)なのだ。
なお、恥を忍んで言えば、読んでいて思わぬ「発見」もあった。これは続で。
- Comments: 0
60キロ台目前!
- 2015-03-30 (Mon)
- 総合
すっかり春めいてきた。昨日は暑いほどだった。マンション5階の私の部屋は西日が凄いので午後遅い時間帯になると、本当に汗ばむほどになる。昨日はプールで泳いだ後、帰宅してまたすぐにスポーツジムに出かけ、風呂に浸かりたい衝動に駆られた。真夏ならそうしたかもしれないが、さすがにまだ3月だ。
陽気がよくなったこともあって部屋の片づけに重い腰を上げているところだ。恥ずかしい話、奥まった和室にはまだ段ボールからあけたばかりの衣服やら書籍やら、こまごまとしたものが散乱している。このマンションに越してきて2年と半年。いくらなんでもそろそろ、片づけなくては。今年からは遠路やってくるかもしれない親しい友人ぐらいは泊めてあげられる程度のさっぱりした住まいにしたい・・・。
長年の会社員生活でスーツやコート、シャツが少なくない。退職以来、一度も着ておらず、これからも袖を通すことのないだろう衣服とはおさらばしたいのだが、可燃ごみとして捨てることは済まない思いが募って今日まできた。これからは「心を鬼」にして少しずつ処分していかなくては。先日はネームの刺繍の入っていないコートを古着ショップに持っていったら、「200円」で引き取ってくれた。捨てるよりはましだ。
書籍は捨てたくない。再読することもあるかもしれないし、以前にも書いたが、読んだことのない本を初めて手にして思わぬ「発見」があることもしばしばだからだ。世にはこれを「積読」(つんどく)というらしい。英訳だと “buying books but leaving them unread” とネットに載っている。私は以前のコラムで “buying books for future reading” と訳したいと書いたが、あれ以来、まさに積読の益に浴している。不思議なのはその本をなぜ自分が購入したのか理由が明確に思い出せないこともあることだ。
それはともかく、部屋を片付けようと思っている理由の一つは、これまで倉庫同然だった和室が夏は実は一番快適な部屋になることを知っているからだ。板張りの洋室は上記の通り、西日が差し込み、寒い冬は夕刻からぽかぽかとしていいのだが、これからの季節は居心地がすこぶる悪くなる。温度を測ったことはないが、洋室と和室の温度差はかなりあるようだ。そのことに気づいて以来、夏は和室に寝転がって読書したいと思っていたが、いかんせん、荷物が散乱していてとてもそういう気にはなれなかった。
それでこのところ、少しずつ不要な物を整理して、ようやく本日、気持ちよく寝転がれるスペースを確保した。窓を開け放つと、気持ちいい風が吹き込んでくる。ベッドではなく、ここに布団を敷いて寝ることも可能となった。こんなささやかなことでも幸せに思わずにはいられない。私はどうも「安上がり」の人間に生まれついているらしい。
古い書類を整理していて、平成5年の人間ドックの診断表が出てきた。22年前だ。体重欄を見ると、72キロと記されている。断酒を続けている今、体重は70キロ台にまで落ちている。おお、30歳代後半の体重にまで改善したことになるではないか。よし、60キロ台突入を目指そう。断酒の他はこれまでと同様の生活を続けながら、少しずつ体重を落としているのがみそだ。最近はプールで一緒になるおばちゃんたちからも「あら、お兄さん、痩せたんじゃない?」などと言われている。いやあ、照れるなあ・・・。
- Comments: 0
日本語が亡びる?
- 2015-03-26 (Thu)
- 総合
徳島で毎春行っている講演会がまた近づいてきた。今年は英語の学習法みたいなテーマで話をする予定だ。文部科学省は2020年を目標に小学3年生から英語を教える方針だとか。そういうご時世もあってか、書店の棚には英語学習の指導書があふれかえっている。
こうした英語の早期教育に対し懐疑的意見も少なくない。まだ小学生には教え込むことは他にあるだろうと。コミュニケーションの基本はまず母国語の日本語でみっちり仕込むべきであるという主張だ。作家の水村美苗氏は2008年にそうした究極的懐疑論を『日本語が亡びるとき 英語の世紀の中で』(筑摩書房)という書で力説している。
水村氏の説によると、今や英語はかつてどの言語も享受しなかった世界全域で流通する「普遍語」という圧倒的立場にある。このままでは世界中の人々が「叡智」を求めようとする時、求めるのは「普遍語」の英語による情報であり、日本語に関すれば「自分たちの言葉」である日本語で書かれた情報は「娯楽」とか「国内スポーツ」のような限定的な情報源としての価値しか持たない危機的状況に陥っていくのが必定という。それは日本語の衰微、日本文学の衰退をも意味する。
水村氏は次のように訴えている。「人間をある人間たらしめるのは国家でもなく、血でもなく、その人間が使う言葉である。日本人を日本人たらしめるのは、日本の国家でもなく、日本人の血でもなく、日本語なのである。それも、長い<書き言葉>の伝統をもった日本語なのである。(中略)日本の国語教育はまずは日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである」。水村氏はそうした前提で、英語教育に関しては国民が広く「平等に」日本語と英語のバイリンガルになる必要はなく、要は国民の一部が(国を代表して)バイリンガルになればいいのであり、そういう教育システムに変革していけばいいのだと提言する。
日本語の大切さは水村氏が指摘する通りであろう。日本語の歴史に関する最近の本を読みたいと思っていたら、恰好の本を見つけた。『日本語の歴史』(山口仲美著・岩波新書)。水村氏は「長い<書き言葉>の伝統をもった日本語」と書いているが、2006年に刊行されたこの本によると日本語の書き言葉はその起源は奈良時代に遡る。山口氏は我々の祖先が「文字」を模索した当時の状況を「日本にはお隣に中国という文化大国があり、政治・経済を含めてすべてを取り入れ、吸収せざるを得なかったといった方がいいかもしれません。中国には紀元前1500年頃に発生した漢字が存在しています。尊敬している国に漢字という手本がある。それっ、というわけで、よくも考えずに日本が漢字を借りてしまうのはごく普通の道筋です」と記している。
日本語は書き言葉に限定すれば、たかだか千二、三百年の歴史しか有していないことになる。人類全体の壮大な歩みの前には瞬間的な時の長さだろう。山口氏は次のようにも書いている。「日本語の歴史をたどってくると、現代の私たちは、過去の人々の大変な努力を知らずに享受していたことに気づいたと思います。最もすばらしい過去からの贈り物は、日本語の文章です。漢字かな交じり文を採用し、言文一致を完成させてあるのです」。
日本語の素晴らしさを後世に伝えていく一方、国際社会で堂々と英語で渡り合い、国内では英語の氾濫にも御していく。そういう社会を築きあげていかなければならないのだろう。
- Comments: 2
一葉の『たけくらべ』
- 2015-03-18 (Wed)
- 総合
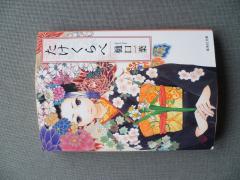
毎日のように拝顔の悦に預かりながら、ついぞその方の作品を手にしたことがなかった。ふとした折にそのことが気になり、先週末再び宮崎の郷里の山里にこもる予定があったので、前日に書店でその本を買い求め、新幹線経由高速バスの車中の人となった。
その方の名は樋口一葉。そう、五千円札にその肖像画が印刷されているお方だ。名前はもちろん知っている。明治の人だろうぐらいのことも。代表作に『たけくらべ』という名作があることも。ただ、悲しいかな、その作品を何であれ、読んだことはなかった。昔、国語の教科書の中に取り上げられていたことはあったかもしれないが、残念ながら記憶にない。記憶に残っていないということは、そういう事実がないか、こちらの当時の学力不足で印象に残っていないということだろう。
書店に行って驚いた。彼女の作品はさまざまな版があるのだ。現代語訳というのもあるのだろう。表表紙の乙女につられたわけではないが、集英社文庫の『たけくらべ』を購入した。消費税込みで380円。本題の作品の他、『にごりえ』『十三夜』の二作も収められていた。
帰福した今も現代では味わえない、不思議な魅力の和文の読後感に浸っている。『たけくらべ』の書き出しは・・・
廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お歯黒溝(どぶ)に燈火(ともしび)うつる三階の騒ぎも手にとるごとく、明けくれなしの車の行来(ゆきき)に、はかり知られぬ全盛をうらないて、「大音寺前と名は仏くさけれど、さりとは陽気の町」と住みたる人の申しき。
当時の吉原(遊郭)の賑わいの様子が目に浮かぶようだ。作家樋口一葉は明治5年に生まれ、29年にわずか24歳の若さで肺結核に没している。西暦では1872年―96年だから19世紀末をあっという間に駆け抜けた作家ということになる。文庫本の解説を読むと、彼女は貧しい家に生まれたわけではなかったが、公教育は小学校で終了し、その後、父親や長兄が相次いで死去し、家運が傾いたこともあり、母親と妹を養う戸主の立場に立たされ、苦労したようだ。夜はまさに文明開化。文学の世界も西洋文明の大きな影響を受けていくが、彼女は西洋文明に感化されることもなく、昔ながらの和文で作品を執筆する。代表作は死去前年の明治28年の一年間にどっと生み出されたものだった。肺結核が今のように不治の病でなかったらと思わざるを得ない。

『にごりえ』の中では伏線として遊女に弄ばれ、身代をつぶし、妻子に苦労をかける亭主を抱えた女房が登場する。亭主の更生を願い、内職仕事に精を出し、何とか一家を切り盛りしようとするけなげな女性だ。読者(私)は彼女に同情を禁じ得ない。次のような女房の心の内を記した一節がある。
「十年つれそうて子供まで儲けし我に、心かぎりの苦労をさせて、子には襤褸(ぼろ)を下げさせ、家とては二畳一間のこんな犬小屋、世間一体から馬鹿にされて・・・我が情婦(こい)の上ばかりを思いつづけ、・・・浅ましい、口惜しい、愁(つら)い人」と思うに中々言葉は出ずして、恨みの露を目の中(うち)にふくみぬ。
恨みの露を目の中にふくみぬ・・・。何という素晴らしい文章だろうか。
(上の写真、嗚呼私にはこの写真を縦にするテクがない! 下の写真は山里で椎茸取りに励む私。昔買ったスキーウエアが山仕事に役立つとは!)
- Comments: 0
フォックスキャッチャー
- 2015-02-28 (Sat)
- 総合
土曜日の朝。本来なら、前回記したように、鹿児島・南大隅町に向かうべく、長旅の途上で読む本をバッグに詰め、そろそろ出ようかと思っているところだろう。ところが前回のブログをアップした直後に町役場に勤務する旧知のTさんから携帯に残念な電話が入った。Tさんの説明によると、この日曜は役場の外での仕事があり、彼自身が忙しい。稲生岳神社の地元の世話役の人も忙しく、伝統の行事はうちわで済ませるような案配だとか。心はすっかり南大隅町に飛んでいたのでがっかりだったが、致し方ない。Tさんとはいずれ機会を見て、稲生岳に参詣登山することを申し合わせて電話を切った。
そんなこんなで時間がまたできた。読みたい、読まなくてはならない本がたまっているので、持て余すことはない。そうだ。映画も久しく観ていない。何か、面白そうなものでもかかっていないかな? いつも足を運ぶ映画館は天神にあるKBCシネマ。こじんまりした映画館で、私はここが好きだ。ネットで調べると、アカデミー賞で5部門にノミネートされた「フォックスキャッチャー」という作品が上演中とあった。「カポーティ」「マネーボール」で知られるベネット・ミラー監督の最新作だとか。私は上記の二作とも映画館で観ている。「カポーティ」はなかなかの力作だった。
この映画は実話に基づく作品だという。1988年のソウル五輪の直前。前回ロサンゼルス五輪のレスリングで金メダルを取った若者、マーク・シュルツにデュポン財閥の御曹司ジョン・デュポンが声をかける。「私はレスリングの大ファンだ。私が作るレスリングチームに加わってくれないか」と。申し分のない年俸とトレーニングセンター。マークは飛びつくが、彼自身の兄で同じレスリングの金メダリストのデイヴもコーチとしてチームに加わったことから、マークとジョン・デュポンとの関係は微妙に変化していく。マークはデュポンの期待を裏切り、ソウル五輪で敗退。デュポンの失望はデイヴに対する憎しみに変貌し、銃口を向け殺害する。その名を世界に知られた大富豪による金メダリストの殺害事件は恐らく当時のアメリカを揺るがした大事件となって報じられたのだろう。私はこの時、アフリカを駆け回っていたせいか、この事件のことは全然知らなかった。
感想を正直に書こう。(統合失調症を患う)孤独で独善的な男ジョン・デュポンが常人の理解しがたい犯罪行為に出る背景に母親に対する癒されぬ思慕の念があることがうかがえるのだが、その描写があまりにも淡々としていて物足りなかった。主要登場人物の演技は見事だったものの。
英語表現で参考になったことが一つ。ジョン・デュポンが日曜日にデイヴの家を訪れるシーンがある。デイヴは愛妻、二人の子どもたちと戯れている。「今日はトレーニングをしないのか?」と責めるかのような不機嫌なデュポンにデイヴは言う。”Today’s Sunday. It’s a family time.” 東京での英字新聞勤務時代にネイティブの同僚に指摘されたことがある。「日本人は父親が休日に家族と過ごすことをよく(和製英語で)ファミリーサービスというが、私は違和感を禁じ得ない。どこか卑猥な印象さえ受ける」と。なるほど ファミリーサービスは正しくは “a family time” なのか!
とここまで書いてきて、ふと思った。ジョン・デュポンが銃口を向けたのがマークではなく、兄のデイヴだったのは、仲睦まじく家族で遊び興じるデイヴの姿に自分が子供時代にそして今も味わえていない家族の温もりを見て、嫉妬に駆られていたからではないかと・・・。
- Comments: 0










