英語でさるく 那須省一のブログ
lame duck より強烈な zombie
- 2016-07-05 (Tue)
- 総合
 ふうぅー、暑い。じっとしているだけで汗が噴き出してくる。昨夏はアイスクリームの類はなぜか全然口にしなかったが、今夏はこのところ毎日のように買い求めている。美味いアイスキャンデーを見つけてしまったこともある。杏仁豆腐とかいうアイスキャンデーで1個140円。あっさりした口当たりで、食べようと思えば幾つでも食べられそう。体重が「高値安定」の身には遠慮したいのだが、プールで泳いだ帰りについつい買ってしまっている。せめてもの抵抗は1日1個の「縛り」ぐらいだ。これもそのうち怪しいが。
ふうぅー、暑い。じっとしているだけで汗が噴き出してくる。昨夏はアイスクリームの類はなぜか全然口にしなかったが、今夏はこのところ毎日のように買い求めている。美味いアイスキャンデーを見つけてしまったこともある。杏仁豆腐とかいうアイスキャンデーで1個140円。あっさりした口当たりで、食べようと思えば幾つでも食べられそう。体重が「高値安定」の身には遠慮したいのだが、プールで泳いだ帰りについつい買ってしまっている。せめてもの抵抗は1日1個の「縛り」ぐらいだ。これもそのうち怪しいが。
◇
NHKのラジオ講座を聞くのが日課となった。朝の講座は韓国語と中国語が連続しているので都合がいい。聞き始めたばかりだから大層なことは言えないが、韓国語に関してはこれまでの独学で覚えた語彙もあり、スムーズに聞ける。ただ、どちらの講座も4月開講だからすでに60回を超えており、「中途入学」の私は必死に耳をそばだてている。韓国語講座のテキストに掲載されている講師の顔写真を見ると、英字新聞勤務時代の先輩同僚によく似ている。何だか親近感を覚える。
前にも書いたが、英語はNHKのラジオ講座にお世話になった。まさか、還暦を過ぎて、今度は韓国語と中国語でもお世話になるとは思わなかったが、継続は力なりだ。どこまで力をつけることができるか自分でも楽しみではある。
◇
英字紙「ジャパン・ニューズ」を読んでいて、懐かしい表現を目にした。記事は提携紙の英タイムズ紙の転電で、ブレグジット(Brexit)の成立で苦境に立つキャメロン英首相が欧州連合(EU)の首脳会議での「最後の夕食会」に参加した際の他国の首脳の反応を伝えていた。国民投票に打って出て、墓穴を掘った格好のキャメロン氏に対する風当たりは強い。首脳の一人は辞任を表明したキャメロン氏のことを次のように評したとか。“After all, he’s a political zombie, in office but not in power.”(詰まるところ、彼は政治的には死に体の人間であり、政権の座にはあるが、権力を行使できる状態にはない)。zombie(死体)とは凄い。マイケル・ジャクソンの「スリラー」が頭に浮かんだ。
懐かしいと感じたのは、生のニュースで後半の表現に初めて出合った時のことを思い出したからだ。1993年のロンドン支局勤務時代、当時のメージャー政権下で財務大臣だったノーマン・ラモント氏が財務大臣職を事実上解任された時に、彼がメージャー首相の政権運営を恨みがましく評した言葉がまさにこの表現。ラモント氏はメージャー首相が英国民に “being in office but not in power” という印象を与えていると言い放ったのだ。彼のこの言葉は英メディアで何度も繰り返し報じられた。私はなるほどこういう表現もあるのかと思った。日本語でピタリと当てはまる気の利いた表現は当時も今も思いつかない。
上記の記事の中では各国首脳はキャメロン氏に対する怒りを直接口にすることはさすがになかったものの、深い失望感は隠せなかったようだ。首脳の側近の一人の次の言葉が彼らの気持ちをよく物語っている。“The referendum was his idea and he’s broken the EU.”(国民投票は彼が自ら言いだしたことだ。彼はその結果、EUを壊してしまった)
- Comments: 0
遂にクーラーをオンに!
- 2016-07-02 (Sat)
- 総合
7月の声を聞いて、本格的に暑くなった。部屋に置いている温度計も遂に30度を超すようになった。何度も書くが、深夜になっても、私の部屋はこのまま、いや逆により温もった状態で、嫌になってしまう。日中は少々の暑さは我慢できるが、夜中はさすがに。そろそろクーラーをつけても罰当たりではないだろう。
それで先ほど、今年初めてクーラーのスイッチをオンにした。このクーラーは購入して3年になるが、自動できれいにする仕組みとかで、私はこれまで一度も中を掃除していない優れものだ。涼しい風が舞い下りてくる。ああ、涼しい。これで今夜から少しは寝苦しさから解放されるかな。文明の利器は有難い。
◇
日本のメディアでも小さく報じられたようだが、7月1日は英仏では大きな記念日だった。第一次大戦で最も過酷な戦いが繰り広げられたフランス北部のソンムの戦い(Battle of the Somme)が開始された日から数えて丁度100年になる日。ロンドン支局勤務時代に、このソンムの戦いに材を取った劇を観たことがある。詳しい内容は覚えていないが、ドイツと闘うためにフランスに向かう英国の兵士の若者の胸中を描いた劇で、とても陰鬱な印象が記憶に残っている。1日に現地の戦場跡地で催された記念式典には英仏のキャメロン、オランド両首脳が顔をそろえて祖国に命を捧げた先人たちに哀悼の意を表した。
ソンムの戦いでは初日だけで英軍の死者は1万9千人以上に達し、英軍史上で最も多大な犠牲者を出した日とされる。100年前の当時の欧州では恐らく今の英国のEU(欧州連合)離脱のブレグジット(Brexit)は比べものにならない衝撃的な出来事だったのだろうなどと思いを馳せていると、バングラデシュから邦人を巻き込んだイスラム過激派によるテロ事件のニュースが飛び込んできた。詳細はまだ不明だが、痛ましいテロのようだ。ソンムの戦いに参加することを余儀なくされた兵士たちの心中は想像できる。しかし、イスラム過激派に身を投じ、無辜の人々を無慈悲に殺害する狂信的な若者たちの心の中は想像することができない。
◇
辛いニュースが続く中、時折、ほんわかした話題を見つけると、手がとまるというものだ。アメリカの自治体の図書館で退去を迫られていたネコに対し、ネコ大好きな人々の間で同情論が湧き起り、図書館内で引き続き居住できることになったという。ただ、それだけのことだが、思わず、笑ってしまったのは、この話題を伝える英文記事のユーモアだ。インターネット新聞「ハフィントンポスト紙」の記事で Weird News (風変わりなニュース)として報じられていた。見出しは Browser The Cat Allowed to Stay at Texas Library。ネコの愛称が「ブラウザー」というのも面白い。「雑学ネコ?」。本文に次のようにあった。
A Texas town council voted on Friday not to evict a cat from the local library, reversing itself and averting a possible cat-astrophe.(テキサス州の町評議会は図書館に住みついていたネコを追い出す措置を撤回する決定を下し、迫っていた大惨事を回避した)。大惨事を意味するcatastrophe にハイフォンを入れ、cat を強調している遊び心が粋だ。
- Comments: 0
語学はイメージ力
- 2016-07-01 (Fri)
- 総合
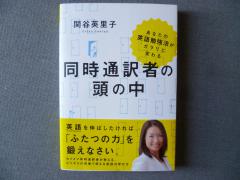 例によって備忘録的読書ノート。『同時通訳者の頭の中』(関谷英里子著・祥伝社)を読んだ。書店で目に入ったので購入したが、今年出たばかりの本だ。表紙には「あなたの英語勉強法がガラリと変わる」という文言が付記されている。帯にはさらに「英語を伸ばしたければ、『ふたつの力』を鍛えなさい。カリスマ同時通訳者が教える、ビジネスの現場で使える英語の学び方」とうたってある。
例によって備忘録的読書ノート。『同時通訳者の頭の中』(関谷英里子著・祥伝社)を読んだ。書店で目に入ったので購入したが、今年出たばかりの本だ。表紙には「あなたの英語勉強法がガラリと変わる」という文言が付記されている。帯にはさらに「英語を伸ばしたければ、『ふたつの力』を鍛えなさい。カリスマ同時通訳者が教える、ビジネスの現場で使える英語の学び方」とうたってある。
著者の関谷氏は日本通訳サービス代表。NHKラジオ講座「入門ビジネス英語」で人気を博し、彼女が催す英語セミナーは常に満席とか。カリスマ同時通訳者として知られ、サンフランシスコ在住と紹介されている。
読んでみて、同時通訳者の頭の中がそう見えたわけではなかったが、参考になったことがあり、以下に記しておきたい。
著者は第1章の「同時通訳者の頭の中」の項で次のように書いている。「私」の中は目や耳から得たスピーカーの情報がイメージ(映像)となって浮かび上がり、そのイメージを私は言葉にします。(中略)ある言語の言葉を別の言語の対照する言葉に直すという作業ではなく、ある言語で表現されたことが瞬時に映像、イメージとして頭の中に映し出され、それを別の言語で表現します。つまり、同時通訳者の頭の中を再現するには「イメージ力」が鍵になってきます。
さらに次のような指摘もある。「イメージ力」は、一朝一夕にはつきません。たくさんの単語と出会い、それらを掘り下げることでしかイメージする力はついていかないため、こうしたひとつひとつの積み重ねが総合的な力になって、英語で話された内容を「言葉」としてではなく「イメージ」、要は情景や映像でとらえやすくなるのです。
これは私も同感。私には同時通訳者のような離れ業はとてもできないが、小説などを読んでいて、特に難解な個所に差しかかった際などには、書かれている情景を頭の中に映画の一コマのようにイメージすることがある。文章が難解であればあるだけ、この方法は役立つかと思う。逆に言えば、映像やイメージとして頭に浮かべにくい描写はあまりいい文章ではないのではとさえ思う。私はそう考えている。
授業でよく引き合いに出すのは、トルーマン・カポーティの名作 “In Cold Blood”(邦訳『冷血』)の結末部だ。拙著『アメリカ文学紀行』でも書いたが、結末のくだりは私には一幅の絵画を観ているような感覚に陥る。少女から大人に成長した娘が足早に霊園を去って行くシーンが頭に浮かぶ。いつかこのような冴えわたった文章を書いてみたいとも願う。(『文学紀行』で紹介したそのくだりは続で)
関谷氏は次のようにも注意を喚起している。似たような指摘は他の本でも目にしている。この指摘は日本人には女性でも男性でも同じことが言えるような気がしてならない。英語を話すとき、私は日本語で話すときよりも低めの声で話しています。もともとアジア人、日本人の風貌は実際の年齢よりも若く見られがちなので、声が高いと子供っぽい、頼りない印象を相手に与えてしまうからです。(中略)日本では人気の「かわいい」ですが、欧米のビジネスの世界ではそれほど評価されません。
- Comments: 0
サブリミナル効果?
- 2016-06-28 (Tue)
- 総合
韓国語ドラマを見ていると、よくラーメンを食べるシーンが出てくる。韓国語だとラーメンは라면(ラーミョン)。驚くのは容器に移さず、鍋からそのまま食べる光景に出くわすことだ。美人の女優さんもしかり。舌や唇をやけどしないのだろうかなどと心配になる。カップラーメンもよく出てくる。勤めていた頃にはインスタントラーメンやカップラーメンはよく食していた。会社を辞めて以降はなぜか遠ざけている。おそらく、きちんとした食事をせねばという意識が働いているのだろう。だから、コンビニで衝動的にインスタントラーメンを買っても、何か月も手をつけずに置きっぱなしにしている。
 これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。
これもサブリミナル効果(subliminal effect)と言うのだろうか。つい先日、韓国語ドラマの食事場面に誘われたかのように、コンビニでカップラーメンを買ってしまった。これは特売のコーナーにあって、ふと見ると、229円のものが特売で180円となっていた。「博多とんこつラーメン大盛」と銘打ってある。とんこつはそう好みではないのだが、カップラーメンで定価が200円を上回るとは何と贅沢な!という思いも手伝い、つい手を出してしまった。それでもまだ熱湯を注いではいない。その日が来るのが楽しみなような・・・。
◇
らっきょう酢の素晴らしさについては何度か書いたかと思う。残念なのはこれは私がよく利用するコンビニには置いてないことだ。少し距離のあるスーパーに行かないと購入できない。それで先日、スーパーに行くのが面倒なのでコンビニで代替品を買った。穀物酢というものが置いてあるのを知っていたからだ。同じ酢だし、穀物という響きも悪くないと考えた。それで、例によって、ゴーヤ(ニガウリ)とゴボウを穀物酢に入れてみた。二晩ほど経過して冷蔵庫から取り出し食してみると————。よく分からないが、らっきょう酢のときほど食欲をそそる味ではなかった。やはり、らっきょう酢が一番のようだ。この夏はらっきょう酢漬けの野菜で乗り切ろう!
◇
アメリカのインターネット新聞「ハフィントンポスト」紙をのぞいていて、気になる記事を見つけた。見出しは “Jumping the gun” とあり、“Brexit will maybe never happen…” と続いている。まだブレグジットが確定したわけではない、早まることなかれ、という感じだ。本文の中には次のような文章があった。Because the referendum is not legally-binding, some politicians are suggesting vote before formally triggering Brexit.
確かに、先の国民投票には法的拘束力がないことは誰もが認めていることである。英国内では今、EU残留を求める多くの国民が2回目の国民投票を求め始めたとの報道もある。英国の法律ではEU離脱は最終的には英議会が承認して初めて成立することから、英国を構成するスコットランドで残留に反対する声が多数派だったことなどもあり、英議会が土壇場で離脱阻止に回り、残留する可能性がないわけではないという。本当? 果たして、予期せぬ大逆転劇がまだ残されているのだろうか。期待したくはなる。
- Comments: 0
EU激震
- 2016-06-26 (Sun)
- 総合
株価の急落など世界中に激震の余波を及ぼしている英国の欧州連合(EU)離脱を決めた国民投票。EU諸国の指導者層からは英政府に対する厳しい視線が注がれている。今後の離脱交渉はかなり冷ややかなものとなりそうだ。そうした空気を伝えるNHKテレビや英BBCのニュースを見ながら、私は英国の文豪、H.G.ウェルズが書いた未来小説 “The Shape of Things To Come” を思い出していた。『世界はこうなる』(吉岡義二訳・明徳出版社)という邦訳本もある。
第二次大戦勃発前の1933年に書かれ、日本の軍国主義、中国侵略、そして敗北など、現代に住む我々が今読んでも「予言は当たった」と感じることの多々ある興味深い小説だ。22世紀初頭までの未来が描かれていて、そこでは試行錯誤の末に人類が行き着いたのは「世界国家」(world state)だったことが記されている。残酷な世界大戦を体験した人類が自分たちの愚かさに気づき、争いを根絶するためにその元凶である国民国家を廃絶して「世界国家」を樹立するという筋立て。今我々が知っている「国民性」は無意味なものとなり、対立をあおる「宗教」も捨て去られ、英語が「世界共通語」として確立される。教育にしても「世界国家学校」という学校を除いてはいかなる学校も存在していなかった。人類のサバイバルを願う究極的な夢物語と言えようか。
私は拙著『イギリス文学紀行』でウェルズの短編 “The Time Machine”(邦訳『タイムマシン』)を取り上げた。こちらの作品では病気や飢え、争いを克服し、何不自由なく幸福に暮らす西暦802,701年の人類の姿が描かれている。ウェルズは1866年に生まれ、1946年に没しているが、時代のかなり先を歩んだ作家だったようだ。『文学紀行』の中ではウェルズに詳しい大学講師に話を伺っている。ウェルズの政治信条は我々が国民国家に固執する限り、人類の未来はないというものだった。だから、国家の枠組みを克服して、「世界国家」を樹立すべきと訴え続けた。そうでなければ、人類は破局に向かうことになると。
ウェルズから見たら、最終的に政治的統合をも視野に入れた今のEUは「世界国家」への礎みたいなものと映るかもしれない。そうした統合の動きが母国の国民によって頓挫させられる結果となった。『文学紀行』でも書いたが、彼は死去する何年か前に墓碑銘には何がいいかと尋ねられ、“Goddam you fools, I told you so!”(くそっ、君たちはなんて馬鹿なんだ。私はそうなると何度も言ってただろ!)と答えたとか。
英国の前途は極めて視界不良。第一、連合王国である英国の存続自体も危うくなった観がある。肝心の経済も英国債の格付けを見直す動きが相次いでいるほか、海外の金融大手が英国の従業員数を削減する検討に入ったとも報じられている。離脱を選んだ反EU派の人々は国民投票日だった「6月23日はこれから英国の独立記念日となる」と意気盛んなようだが、果たして彼らの目論見通りに推移するのか。
サイエンスフィクションの父とも称される文豪が今の英国民を見たら、果たしてどのような言葉をかけているだろう。私にとってイギリスはまた住んでみたい国だし、ロンドンもいつか再訪したい。友人もいる。文豪の口から発せられるのが “Goddam you fools, I told you so!” という言葉でないことを願う。
- Comments: 0
NHKラジオという手があった!
- 2016-06-24 (Fri)
- 総合
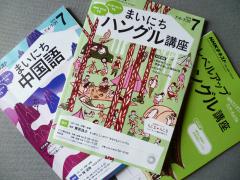 韓国語と中国語の独学。ふと思い出した。NHKラジオでも初級者向けの番組を放送しているはずだと。早速金曜朝の韓国語の初級を聞いてみる。思った以上に聞き取ることができた。あ、これなら自分の勉強に必ず役立つぞと嬉しくなった。続いて聞いた中国語の初級クラスはさすがに難しかったが、歯が立たないという感じではない。
韓国語と中国語の独学。ふと思い出した。NHKラジオでも初級者向けの番組を放送しているはずだと。早速金曜朝の韓国語の初級を聞いてみる。思った以上に聞き取ることができた。あ、これなら自分の勉強に必ず役立つぞと嬉しくなった。続いて聞いた中国語の初級クラスはさすがに難しかったが、歯が立たないという感じではない。
書店で来月のテキストを買い求めた。「まいにちハングル講座」と「まいにち中国語」。韓国語の方は少し背伸びして「レベルアップハングル講座」も買い求めた。これで来月からの聴取態勢は万全だ。なぜもっと早く、NHKの語学講座のことを思いつかなかったのだろう。私はパーボ(韓国語で馬鹿)だった。(♪僕の名前はパーボー、君の名前もパーボー♪と、私は炊事をしながら歌っている)
高校時代、NHKラジオの英語会話講座にはとてもお世話になった。下宿生活でラジオ放送を可能な限り聴いた。発音の細かなところは分からなかったものの、個々の語彙を段々と聞き取れるようになっていった。リスニング力がついたのを自覚したのは、最初の頃は全然理解できなかった日本人の先生とネイティブスピーカーの教科書を離れたフリートークが分かるようになったときだ。高校3年生になっていたかと思う。
釜山訪問は自粛しているが、7月か8月初めには3回目の旅をしたいと考えている。そのときは少しは自由に喋れるようになっているはずだと期待している。
◇
びっくりする結果となった。英国が欧州連合(EU)に残留すべきか離脱すべきかを問うた国民投票は、何と離脱派が勝利した。英国民はEUへの不満は数々あったとしても、最後には残留を選択するというキャメロン首相の戦略は破綻した。私も最終的には残留派が勝利すると思っていた。まさか、このような結果になるとは・・・。
結果が判明したばかりだから、どのような政治的、経済的な影響が出るかはまだこれからのことだ。それにしても冷静沈着な英国民がこのような選択をするとは意外だった。金曜日は終日、ケーブルテレビのBBC放送に見入る羽目となった。そこで懐かしい顔を目にした。離脱派のビル・キャッシュ議員(保守党)。新聞社のロンドン支局勤務時代に彼には何度か取材した。メガネの奥の目をギラギラさせながら、反EUの主張を熱っぽく論じていた。少しマニアックな印象のある人物だった。あれから20余年後、まさか、御年76歳のその彼が勝利の予感に興奮気味で反EUの持論を繰り返すのを目にするとは・・・。
これから専門家諸氏が離脱派が勝利した背景とか、今後の英国の進路、EUの展望とかを語ってくれるだろう。現時点で私が思うのは、英国民の多くが自分たちの国の運営は自分たちだけでやれる、何もわざわざ海峡を隔てた他の国々に指図されることはないというプライドが離脱を選んだのではないかということだ。EUとの絆を自ら断った孤高の国を待ち受けるのは繁栄か苦難か。
中東からの難民問題など、苦境に立つEUにとって大打撃となったことは間違いない。反EU機運が高まっているのは英国だけではない。今後、同様の国民投票が実施される可能性も否定できない。英国の矜持を象徴する存在ともいえる、元首相のチャーチル氏やサッチャー氏が黄泉の国から今回の英国民の判断にどういう評価を下すか、知りたいものだ。
- Comments: 0
コロケーションについて
- 2016-06-22 (Wed)
- 総合
寝苦しい夜が続いている。クーラーが恋しい。もうそろそろ「白旗」を挙げたくなった。いや、あと一週間ちょっとは我慢だ。7月になったらリモコンのスイッチを入れようなどと気持ちが揺れている。日中は窓や玄関のドアを開け放すことで風が通り、風鈴も涼やかな音色を奏でてくれるので何とかやり過ごすことができるのだが。昼間だと28度前後の室温が深夜でも下がらず、逆に30度近くになるのだから参ってしまう。日中の熱が部屋の中にこもってしまうみたいだ。今の住まいはとても気に入っており、これだけが難点。
◇
前回の項で『新・至福の朝鮮語』(野間秀樹著)を参考に、膠着語である日本語と韓国語の類似性について記した。先ごろ読んだ『英語で話すヒント』(小松達也著)でもこの件について興味深い記述があった。その部分を適当にはしょって紹介すると・・・。英語ではセンテンスの頭には原則として名詞形の主語がきます。その後に術語としての動詞が続きます。そして(S+V)という核を中心にセンテンスが形成されます。このような言語は「主語優越型言語(subject-prominent language)」と呼ばれます。それに対して日本語は、中国語などとともに「話題優越型言語(topic-prominent language)」に属し、文頭に主語がくることもありますが、主題あるいは話題がくることが多いという特色を持っています。特に「~は」という場合は主題であることが多い。(中略)日本語の専門家の間でよく知られている、いわゆる「ウナギ文」も同じような例です。僕はウナギだ。言うまでもなくこれは、レストランでの食事の注文です。これを何と英語に訳したらいいでしょうか。この「僕」も主語ではなく主題であって、「僕はと言えば、ウナギを注文する」という意味でしょう。直訳すれば “As for me, I’ll have eel.” となりますが、より口語的には、“Could I have eel?” あるいは、“I’ll go for eel.” などとなるでしょう。
拙著『英語でさるく』で私はこれを和製英語の一例と取り上げている。次のように書いている。最近見るともなく見ていたテレビドラマで、日本人の女子高生が米国に旅立ち、街頭で通行人に道を尋ねるシーンがあった。どの交通手段で行くか、地下鉄かバスかと逆に問われて、「私はバスで行く」という意味で、“I’m bus.” (私はバス)と答えて、親切な米国人を辟易させていた。
今なら、上記の「話題優越型言語」に言及して、日英の表現の違いを説明したい。さらに付記するなら、コロケーション(collocation)のことにも触れるかもしれない。コロケーションとは一緒に使われる単語と単語のつながりのことで、「連語」と呼ばれる。どこかの新聞で、韓国の航空会社を利用した際、乗務員が機内アナウンスで「皆さま、窓の外をご覧ください。富士山が丸見えでございます」という趣旨のことを言い、機内が爆笑に包まれたとか。意味は分かる。だけども現実にはそういう言葉遣いはしない。それがコロケーションだ。
私たちは服を身につける時には「着る」、帽子を身に着ける時には「かぶる」という動詞を使い分ける。英語ではどちらのケースもput on とかwearという同じ動詞を使うことが可能。この考え方で、日本語を学んでいる英語のネイティブ話者が「帽子を着る」と言ったとしたら、我々は意味を理解できても、笑ってしまうだろう。それは不自然な言い方だからだ。
- Comments: 0










