Home > 総合
英語でさるく 那須省一のブログ
気になった日本人団体客の描写
- 2022-05-15 (Sun)
- 総合
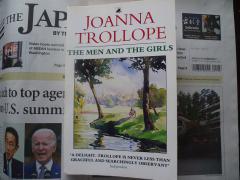 手元にあることを忘れていた、というか全く頭になかった英小説 “The Men and the Girls” は読み始めると面白く、数日で読み終えてしまった。Joanna Trollopeという作家の手になる300頁程度の中編小説。私は本当になぜこの本を購入したのか分からない。ひょっとしたら似たような名前の作家の作品と勘違いして洋書コーナーで買い求めたのかもしれない。時々難解な語彙が出てきて、その都度辞書を引く手間を余儀なくされた。辞書を引いてその意味を納得したが、おそらく大半はもう忘れているかもしれない。
手元にあることを忘れていた、というか全く頭になかった英小説 “The Men and the Girls” は読み始めると面白く、数日で読み終えてしまった。Joanna Trollopeという作家の手になる300頁程度の中編小説。私は本当になぜこの本を購入したのか分からない。ひょっとしたら似たような名前の作家の作品と勘違いして洋書コーナーで買い求めたのかもしれない。時々難解な語彙が出てきて、その都度辞書を引く手間を余儀なくされた。辞書を引いてその意味を納得したが、おそらく大半はもう忘れているかもしれない。
情けなく思うが、これはいかんともし難いことであろう。中国語の語彙でもNHKラジオの講座で何度も目にし、耳にした語彙もその漢字(簡体字)、ピンイン表記、声調を正確に記憶しているのは極めて難しい。例えば「災害」という語。中国語ではザイハイとか何とか呼ぶことは何となく頭に残っているが、これが「灾害」と簡体字で書き、zāihàiというピンイン表記となることは何度覚え(ようとし)てもすぐに忘れてしまう。
とまあそんなぼやきはともかく、“The Men and the Girls” は1992年にロンドンで刊行されている。私が新聞社の支局員としてロンドンに勤務していた頃とほぼ重なる。ともに30代半ばのKate とJuliaの二人の女性、彼女たちの60代前半の伴侶JamesとHughが登場する。テーマは女性の自立を求める心、束縛からの解放を願う心だろうか。
自分の才能を活かすメディアの仕事を満喫することを夫に受諾させたJuliaは、年齢的なこともありMCの仕事の契約を打ち切られ、やけになって家を捨てた夫のHughが反省して戻って来ることを許す。Kate はパートナーのJames、Jamesのさらに高齢の気の難しい叔父のLeonardと同居するようになって8年が経過。彼女には多感な14歳の娘が一人おり、この子育てにも四苦八苦する。さまざまなプレッシャーに押しつぶされた彼女は自ら家を出て、自由な身となる道を選ぶ。ただ一人の生きがいである娘はなぜか、何の血縁関係もないJamesや Leonardとの暮らしを選択する。Kateは新しい恋人に出会うが、心が満たされることはなく、最後にはJamesの元に戻り、それまで頑なに拒否していたJamesとの結婚を自ら求める。ハッピーエンドの結末は出来過ぎと思わないでもないが、就寝時に飽きることなく頁を繰り続けた。
この小説を読んでいて思わず笑ってしまったことがある。おそらくこの作家の日本人に対するイメージがこうした描写を盛り込ませたのだろう。Kateがイタリアンレストランでのウエイトレスの仕事からくたびれ果てて帰宅したシーンの描写だ。… it had been a non-stop day with the restaurant full of tourists, including what seemed like half a busload of Japanese who all ordered exactly the same thing which put Benjie in a temper.
Benjieとはレストランで働くシェフのこと。大挙してお店にやって来た日本人の団体客が同じ料理を注文したことに腹を立てたとか。イタリアンだからパスタでも注文したのだろうか。それも同じ種類のパスタを。シェフの腕前を振るうことができず、憤慨でもしたのだろう。私は80,90年代に日本人の「個性」がいや、「個性」のなさが海外でどう受けとめられていたかを垣間見るような気がした。私もその一人だったかもしれない。今はこのような記述がたとえ小説のたわいないワンシーンだとしても挿入されないように願う!
- Comments: 0
“Sugoi!”
- 2022-05-11 (Wed)
- 総合
 月曜日。ぽかぽか陽気にも誘われてガスヒーターを片付けた。すぐに冷房が欲しくなるのだろう。とりあえずは扇風機でどれだけしのげるか。その月曜日には、今年初めて玄関のドアを開け、窓との通風を試みた。当分は少なくとも日中はこれで精一杯涼みたい。やがてクーラーのスイッチを入れたくなるのは目に見えてはいるが・・。
月曜日。ぽかぽか陽気にも誘われてガスヒーターを片付けた。すぐに冷房が欲しくなるのだろう。とりあえずは扇風機でどれだけしのげるか。その月曜日には、今年初めて玄関のドアを開け、窓との通風を試みた。当分は少なくとも日中はこれで精一杯涼みたい。やがてクーラーのスイッチを入れたくなるのは目に見えてはいるが・・。
よくのぞく八百屋さんに好物のスイカが並ぶようになった。そしてずっと待っていたゴーヤも姿を見せ始めた。らっきょう酢に漬けて一晩冷蔵庫で寝かせれば滋養豊かなピクルスとなる。私の身体は何と安上がりにできていることか。神様にこれも感謝だ。
◇
本棚からあふれた本をソファーのそばに放ってある。処分した方がいいのかなと思ったりしている。連休期間中に既読の本を読み返したこともあって、何冊か手にしてみた。その内の一冊に手が止まった。天神の書店の洋書コーナーで購入したのだろうが、全然読んでいなかった。きっと内容が想像していたのと異なっていたので放棄したのだろう。
“The Men And The Girls” というタイトルの小説で、著者は Joanna Trollope とある。知らないイギリスの作家だ。何でこんな小説など購入したのだろう。私は本を買ったら領収書みたいなものを末尾に挟んでいるが見当たらないので、いつ買ったのか分からない。天神の書店なら東京から福岡に転勤して以後のことだから2006年以降になる。
それで何となく読み始めた。悪くない。あれ、これ、案外面白いのかもしれないと思い始めた。なぜ読まなかったのだろうか? まだ三分の一程度を読み終えたところでこれから物語がどう展開するのか。男女の愛、年齢、仕事と生きがいなどがテーマのようだ。主要登場人物の一人は61歳になる教師のJames。25歳も年下のパートナーで思春期の娘のいるKateと暮らし、結婚を望んでいるが、彼女はそれを断固拒絶している。Kateがミスを犯したJames に向かって罵る場面がある。“You stupid old man.”と。彼女は後になってoldと罵ったことを悔いる。さらにJames の年齢について考えるシーンがある。“Sixty-one isn’t old. Sixty-one’s nothing. It’s very wrong of me to think of James as old.”
今年68歳となり、さてこれからどういうことがまだできるだろうかと思案している身としては、さすがに考えさせられたくだりだった・・・。
◇
ウクライナ情勢が気にかかる一方、米大リーグの大谷翔平君の一挙手一投足もしっかりフォローしている。仕事と重なったため生で見ることはできなかったが、火曜日(日本時間)の活躍は見事だった。初めての満塁ホームランを含む2本の本塁打をかっ飛ばした。木曜日(日本時間)には4勝目を目指しホームグラウンドのマウンドに立つ。ここでも再度好投を見せるようだとショーヘイフィーバーはいよいよボルテージが上がるだろう。
そう言えばパソコンで見た大リーグのダイジェストビデオでは翔平君の満塁ホームランを実況していた現地のアナウンサーが一言 “Sugoi!” と叫んでいた。翔平君がこれからも活躍を続ければ、“sugoi” (凄い)という語がやがて英語(米語)の新語として仲間入りする日が来るかもしれない。
- Comments: 0
『坑夫』の違和感
- 2022-05-05 (Thu)
- 総合
 ゴールデンウィークも終わりに近い。たかだか一週間にも満たない連休をゴールデンウィークと呼ぶのは気恥ずかしい気がしないでもない。100年後の日本人がこの時代を眺めたら、どう感じるのだろうか。もっとゆっくり休暇を取れよと思うのか。ご先祖様はなんとつましい暮らしをしていたものよと苦笑するのだろうか。まあ、一線を退いた私は毎週がゴールデンウィークみたいなものだからあまり御託を並べる資格はないが・・。
ゴールデンウィークも終わりに近い。たかだか一週間にも満たない連休をゴールデンウィークと呼ぶのは気恥ずかしい気がしないでもない。100年後の日本人がこの時代を眺めたら、どう感じるのだろうか。もっとゆっくり休暇を取れよと思うのか。ご先祖様はなんとつましい暮らしをしていたものよと苦笑するのだろうか。まあ、一線を退いた私は毎週がゴールデンウィークみたいなものだからあまり御託を並べる資格はないが・・。
それでも仕事の準備から解放されるこのゴールデンウィークは久しぶりに伸び伸びと過ごすことができた。天候にも恵まれた。押し入れの布団、毛布をベランダで干し、洋服ダンスの衣服も陰干しすることができた。大リーグにプロ野球を堪能したし、夜には長いこと観ることのなかったケーブルテレビの洋画劇場も楽しんだ。
東京勤務時代にはゴールデンウィークには宮崎の田舎に里帰りして長姉夫婦の山仕事をよく手伝った。山仕事の朝は早い。朝6時にはたたき起こされていた。折角の休暇が休暇の意味をなさなかったが、そう苦ではなかった。普段ふしだらな生活を送っていたことへの「罪滅ぼし」の意識があったのかもしれない。
◇
夏目漱石の『坑夫』を読んだ。読みながら、なぜ以前にこの小説を投げ出したのか分かったような気がした。それはそれまで読んできた漱石文学とは性質を異にする気がしたからだろう。高等遊民の世界とは異なる、世間知らずの若者の煩悶が描かれていた。いや、煩悶と表現していいのか迷う。生活に追われている庶民から見たら、自暴自棄の自殺願望で自死の場所を探したあげくに鉱山に行き着いた若者は甘っちょろいと映ることだろう。坑夫の仕事も結局は虚弱さゆえに許されず、楽な帳場の仕事を5か月やっただけで帰京する。
作品中には今の時代には考えられない社会的弱者に対する差別用語が頻出していた。作品が発表された明治41年(1908)には一般的な社会通念だったのだろうが、今読むとさすがに手が止まる。とはいえ、この作品は若き漱石青年の投影ではなく、モデルと見立てた若者を通して当時の鉱山労働者の苦しい生活の一端を描いたものだろう。漱石文学の価値を減じるものでないかとも思う。
読んでいてマーカーを走らせたところが一か所あった。それをここに記す。
偶然の事がどんな拍子で他の気に入らないとも限らない。却て、気に入ってやろうと思って仕出かす芸術は大抵駄目な様だ。(中略)骨を折って失敗するのは愚だと悟ったから、近頃では宿命論者の立脚地から人と交際をしている。ただ困るのは演説と文章である。あいつは骨を折って準備をしないと失敗する。その代わりいくら骨を折っても矢っ張り失敗する。つまりは同じ事なんだが、骨を折った失敗は、人の気に入らないでも、自分の弱点が出ないから、まあ準備をしてからやる事にしている。
スピーチと文章についてはきちんと準備をしないと失敗する。かといっていくら用意周到に準備したとしても結局は失敗する。これは主人公の若者の述懐というより、作家の肉声であるのだろう。私の場合には「骨を折った失敗」であっても自分の弱点が露呈すると思うが、漱石先生にしても文章、スピーチともに難物であったらしい。慰めにはならないが。
- Comments: 0
日本人が英語が苦手な理由
- 2022-05-02 (Mon)
- 総合
日曜日。徳島市の英語愛好者のグループの集まりに参加させてもらい、このところずっと考えている外国語学習の最近の気づきについて話をさせてもらった。「ああ、だから日本人は英語が苦手なんだ!」というタイトルをつけたが、これは「看板に偽りあり」だったかもしれないと集まりが終わった後で反省した。それはともかく、やはり自分の頭の中にあることを言葉にして人前で話すのは得がたい経験であり、これからの学習の参考にもなった。
巷間言われるようにSOVの日本語とSVOの英語、中国語は基本構造からして異なっているが、中国語は日本語や韓国語と同様、話題優越型言語(topic-prominent language)であり、日本語とも共通の特質があることを語った。音韻的には日本語の母音は「アイウエオ」のわずか五つの言語であり、英語はもちろん、中国語や韓国語とも比べても簡素な言語だと説明したかったが、舌足らずだったような気がしないでもない。
私が近くの公民館で参加している韓国語教室。先週の教室でたまたま、ランチ(lunch)という外来語が出てきた。韓国語ネイティブ話者の先生は大きな声で「ロンチ」と発声された。私はロケットでも発射するのかと戸惑った。lunchではなくlaunchと聞こえたからだ。「何か発射したのかな?」と。日本語では「オ」の音は一つだけだが、韓国語では口を大きく開ける「オ」と日本語に近い唇を突き出して言う「オ」の二つの「オ」がある。
我々は lunch をランチと言うが、韓国人はロンチと呼ぶことを初めて知った。英語由来の外来語で我々が「ア」と発声する母音の多くが韓国語では口を大きく開ける「オ」で対処されていることを示している。それだけ彼らは母音のレパートリーが多く、英語を学ぶ上でも「利点」となっているのではないか。若者の食生活には欠かせない hamburger は韓国語のハングル表記では 햄버거 であり、その語「ヘムボゴ」は口を大きくを開ける二つの「オ」の音を含む。英語ネイティブ話者には「ハンバーガー」よりも「ヘムボゴ」の方がより英語らしく聞こえるのではないか・・・。
この日の集まりでも説明したが、中国文学者の高島俊男氏は著書『漢字と日本人』の中で「不器用な日本人」と題し、「日本人の口は不器用だ。日本語は開音節構造である。すべての音節が母音でおわる。しかもその母音の前につく子音は一つだけである。要するに日本人が口から出せるのはごくかんたんな音だけである。またその音の種類がいたってすくない。これはもう大昔からそうである」と慨嘆しておられる。日本人が英語を苦手に感じてしまうのは、我々が今さら嘆いても仕方がないことなのである。
ところで上記の集まりはオンラインで実施された。ズームと呼ばれる。私はこれまでもズームは非常勤講師の仕事の延長線上で利用したことはある。短篇小説を読む私の英語教室ではスカイプと呼ばれるオンラインを利用している。だからもう扱い方に慣れていていいはずだが、いまだに覚束ない。用意したパワーポイントを自分のパソコンの画面一杯に広げると、それまで見えていた参加者の顔が画面から綺麗に消えてしまう。それはそれでいいいのだが、反応が全然見えなくなってしまう。パワーポイントのスクリーンを画面の半分程度に収めるにはどうしたらいいのか。こういうことを今ここで書いていること自体、私はうつけ者(fool, 呆子,바보)に違いない!
- Comments: 3
スターリンの系譜
- 2022-04-30 (Sat)
- 総合
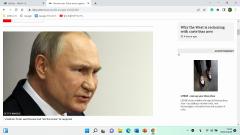 本日は4月最終日。明日からは5月。本当にあっという間に時間が過ぎ去っているような気がしてならない。今年はコロナ禍に加え、ウクライナの信じ難い戦火もあるから、何だか一層そういう気がしているのだろうか。考えたくないが、これに心配される大地震でも起きたら、心中は陰鬱極まりないものとなるだろう。一刻も早くウクライナの人々に安寧の日々が戻り、コロナ禍も収束することを心から願い、そして祈る。
本日は4月最終日。明日からは5月。本当にあっという間に時間が過ぎ去っているような気がしてならない。今年はコロナ禍に加え、ウクライナの信じ難い戦火もあるから、何だか一層そういう気がしているのだろうか。考えたくないが、これに心配される大地震でも起きたら、心中は陰鬱極まりないものとなるだろう。一刻も早くウクライナの人々に安寧の日々が戻り、コロナ禍も収束することを心から願い、そして祈る。
◇
ウクライナ情勢に関しては、先日のジャパン・ニュース紙に「我が意を得たり」の論評記事が掲載されていた。米ワシントン・ポスト紙からの転載で “Xi, Putin twist meaning of ‘peace’ and ‘security’ という見出しが付いていた。
かつてないような蜜月関係にある中露の首脳がウクライナ情勢に関しても見解を同じくしていることを批判していた。内容はほぼ想像のつくものだったが、ウクライナで起きている悲劇はかつてロシアのスターリン独裁時代にも起きていたと説いていた。プーチン露大統領はロシアとウクライナはとても近しい親族関係にあり、両者は一体であるかのように主張しているが、スターリンは第一次大戦後の1930年代にウクライナという存在を地図から「抹殺」するかのような虐殺・圧政を繰り広げたとか。それと全く同じことをやろうとしているのがプーチン現政権だと告発している。
私はウクライナの人々をプーチン氏がよく「ナチ」と非難しているのが不思議でならなかった。ウクライナはユダヤ人を殺戮したナチスとは関係がないだろう、なぜ、そういう呼称を浴びせるのかと。ヒトラー率いるドイツ軍が1941年にロシアに攻め込もうとしたとき、そのルートとなったウクライナではスターリンよりもまだましだとナチスの越境を歓迎する向きもあったのだとか。こうした経緯も盾に取り、プーチン氏はウクライナ侵攻の正当性を主張しているようだ。次のように書かれていた。Yet today, Putin uses that history to persuade his duped nation that the Ukrainians are nothing but Nazis.
論評は我々が今ウクライナで目にしているのは、ジョージ・オーウェル的な倒錯した世界だと断じている。ロシア軍の蛮行が “peace”(平和)を求めてのことであり、ウクライナ人に対する迫害はロシアに “security”(安全)をもたらすのだというプーチン氏の主張を鵜呑みにすることなどできようはずもない。
◇
有言実行ではないが、積ん読状態にあった文庫本を手にしている。夏目漱石の名作の一つと言われる『坑夫』。明治・大正時代を代表する文豪の作品はたいてい読んでいるが、これはずっと以前に書店で買い求め、読み始めたものの、なぜか興味が失せ、ベッドの下に放っておいたままになっていた。
それでベッドの下から取り上げ、読み始めた。読み始めた冒頭に近い部分で、沿道の茶店の女将さんが客応対の間にお店の裏手に回り、松の木に向かって立ち小便をするシーンが描かれていた。昔は世の東西を問わず、立ち小便は男の特権ではなかったのだろう。いやはや、それにしても昔の女性はたくましかったのだなあ!
- Comments: 0
女には「命」の髪の毛が2000円?!
- 2022-04-25 (Mon)
- 総合
 どうなるのかウクライナ情勢。連日NHKテレビが報じているが、ウクライナ周辺の地図はいまもすっと頭に浮かばない。モスクワには取材で一度だけ訪れたことがあるが、東欧と呼ばれる国々には縁がなく、唯一足を運んだことがあるのは旧ユーゴのボスニア・ヘルツェゴビナぐらいか。これが今も正しい国名であるのかさえ自信がない。後でチェックしなくてはならない。
どうなるのかウクライナ情勢。連日NHKテレビが報じているが、ウクライナ周辺の地図はいまもすっと頭に浮かばない。モスクワには取材で一度だけ訪れたことがあるが、東欧と呼ばれる国々には縁がなく、唯一足を運んだことがあるのは旧ユーゴのボスニア・ヘルツェゴビナぐらいか。これが今も正しい国名であるのかさえ自信がない。後でチェックしなくてはならない。
中南米にも取材経験がないので、カリブ海周辺も含め、中南米の国々の位置関係を頭の中に正確に地図として広げるのは難しい。正直に書くと、あまり興味がないので致し方ないかと思う。残り少ない人生、中南米の国々にこれから足を運ぶことはまずないだろう。残念ではあるが。
オンラインで続けている英文小説を読む英語教室。このところ、オー・ヘンリー賞受賞の優秀作品を読み続けている。いずれも短篇の作品なので読みやすいことこの上なし。日曜日に読んだのは “Scissors” というタイトルのベネズエラ出身の女性作家の作品だった。私が購入したペーパーバックの本ではわずか5頁にも満たない短さ。先述した通り、行ったことのない南米を舞台にした作品だから、ネットでベネズエラや隣国の地図や写真をチェックしながら読み進めた。読み進めたといってもあっという間に読了とあいなった。
作品は困窮している祖母、母親、娘の3人が国境を越えたコロンビアの町にバスで行き、自分たちの髪の毛を売って何とか食料品を購入しようとする物語。彼女たちにはもはや頭髪しか売るものは残っていないようだ。私の手が止まったのは次の記述。“We’ll give you sixty thousand pesos for yours, a little less for your mother’s” これは髪の毛を刈り取る業者が娘に言う言葉。自分の髪の毛を売って手にできるのが6万ペソ。コロンビアペソの通貨価値など見当もつかない。ネットで検索して調べてみると、1 コロンビア・ペソ は0.034 円 とあるから、60,000×0.034=2,040円となる。女性にとっては「命」のような髪の毛が2千円ぽっちとは!ベネズエラの人々の困窮ぶりが垣間見える。
折も折、読売新聞の国際面にベネズエラの人道危機が報じられていた。政治的、経済的な混乱から南米の周辺国に逃れる人たちが急増しており、その数はここ数年で全人口の2割に当たる600万人に達しているとか。この国は世界有数の産油国であるにもかかわらずだ。
この作品は不思議なところがあった。不思議というか、何かのミスではないかと思うのだが、ネットでは私が手にしている本には掲載されていないパラが最末尾に少し続いていた。その部分は余韻たっぷりであり、味わい深い終わり方になっていた。ネットでこの部分を読むと、本のエンディングがさすがに物足りなく感じる。この作品はネットでも読めるため、コロナ禍での英語教室には有り難く、だから選んだ事情もある。ネットで確認しなかったら、“Scissors” という作品に対する印象は異なったものになっていたことだろう。
それはともかく読書はいい。語学の勉強に勤しんでいると、それはそれで充実感はあるのだが、辞書で調べるなどして覚えたと思っている語彙を数日後にはすっかり忘れてしまっている。そういうフラストレーションに悩まされる身には読書は気が休まる。依然動きの取れない5月の連休には夏目漱石か志賀直哉の名作を久しぶりに読もうかと考えている。
- Comments: 0
麻雀(観戦)が趣味?
- 2022-04-20 (Wed)
- 総合
 クリスチャンの端くれとして毎朝、ウクライナの人々のために祈り続けている。崇敬している「子羊の群れキリスト教会」のP牧師は我々がいよいよ「終わりの時」を生きていると告げている。それが本当に意味するものを私は理解しているのかはともかく、ウクライナで起きていることにはかつてないほど心が乱されている。私たちが慣れ親しんできた人類文明はもはや過去の「遺物」となってしまうのかとさえ危ぶまれる。
クリスチャンの端くれとして毎朝、ウクライナの人々のために祈り続けている。崇敬している「子羊の群れキリスト教会」のP牧師は我々がいよいよ「終わりの時」を生きていると告げている。それが本当に意味するものを私は理解しているのかはともかく、ウクライナで起きていることにはかつてないほど心が乱されている。私たちが慣れ親しんできた人類文明はもはや過去の「遺物」となってしまうのかとさえ危ぶまれる。
そうでないことを心から願う。来年の今頃、このブログを振り返って、嗚呼、昨年のこの時期はこんなことを考えて過ごしていたのかなどと懐かしく思い出すことになっていればいいのだがと心から願う。神様に日々感謝し、ご加護を祈るしかない。
◇
惰性で聴いているNHKラジオの中国語講座で趣味が話題に上っていた。中国語では「趣味」は「爱好」ということは承知していた。漢字の字面の意味合いから何となく理解できる。韓国語では「최미」ということも。中国語では「趣味」という語はないのかなと思い、辞書を引いてみると「趣味」という語句もあった。ただ、英語の hobby という意味合いでは使わないようだ。「趣味のいいネクタイ」という意味合いの「趣味」であるとか。発音も「チューウェイ」であり、だいぶ印象が異なる。それでもこの「センス」という意味合いでは日中両語で同じ漢字語が使えるとは感動的に思える。
英語では最近は初対面の場などで “What is your hobby?” などとはあまり尋ねないようだ。ぶしつけに聞こえるのだろう。さりげなく “When you have time, what do you do?” とでも聞くのがいいと聞いたような気がする。日本だけでなく中国や韓国では「爱好」や「최미」と真正面から尋ねても問題なさそうに思えるのはなぜだろうか?
◇
最近時々のぞく喫茶店のような食堂。いつも食べるのは決まっている。「カオマンガイ」という料理。タイの料理だろうか。よく分からない。低温調理した柔らかい鶏のもも肉に鶏出汁で炊いたジャスミンライスが風味豊かな味わい。850円。毎日でも食べられる美味さだ。
普段は無骨な自炊の食事で空腹を満たしているから、ときにはこういう美味なランチを味わうと喜びが一層増す。
◇
月曜日の朝日新聞朝刊の紙面。AbemaTVで無料放送されている麻雀プロのリーグ戦の全面広告が賑々しく載っていた。朝日新聞も後援している麻雀のリーグ戦だ。一昔前にはこのような広告が朝日新聞に掲載されるとは思いもしなかった。私は麻雀が好きだが、一人ではできない娯楽だから、もう何年も牌に触っていない。麻雀の勝ち負けは雀士の技量だけでなく、運不運がかなりの重要な要素を占める。麻雀にプロという存在が果たしてあり得るのかという根源的な疑念を私は捨てきれない。
とはいえ、眺めていても面白いのが麻雀。趣味はと聞かれて麻雀(観戦)と胸を張って言える時代か。ただし、競馬同様、麻雀はギャンブルでもあり、油断しているとそこに思わぬ「落とし穴」が待ち構えていることを忘れてはならないだろう。
- Comments: 0
Home > 総合










