英語でさるく 那須省一のブログ
ウクライナに思う
- 2022-03-05 (Sat)
- 総合
ウクライナ情勢は最悪の事態に向かいつつあるようだ。ロシア軍の愚かで無慈悲な攻撃に苦しんでいるキエフや他の都市に住む人々を思うと心が塞ぐ。今回の軍事侵攻が起きるまでウクライナという国はその位置さえ明確に認識していなかった。旧ソ連邦を構成していた国であることは承知していたが、東欧周辺の国には足を運んだこともない。
今回の侵攻でウクライナの人々がロシアと同じ民族系統に属し、言語・文化的にも兄弟のような近い関係にあることを改めて知った。ただ、ウクライナの大多数の人々は欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)に加盟することを望んでおり、ロシアとは距離を置きたいと考えていることも。
プーチン露大統領の心中は知る由もないが、一連の報道から察するに、彼がウクライナの親欧米路線に憤まんを募らせていたことは間違いないだろう。このまま手をこまねいていれば、ウクライナがロシアから完全に遠ざかってしまうという危機感。ソ連邦の崩壊に伴い、独立したウクライナを再び「奪回」し、かつての「帝国」を復活させたいという野望も透けて見える。それにしても都市部の住宅地区への無差別砲撃を繰り返し、あろうことか欧州有数の原発施設にも砲火を浴びせる狂気としか思えない愚挙にまで出ている。そうは信じたくはないが、世界はそして人類はいよいよ黙示録の終末期に入りつつあるのだろうかとさえ思えてくる。
ウクライナ情勢を見ていて、オンラインの英語教室で読んだばかりのオー・ヘンリー賞受賞の短篇を思い出した。David Rabeという名の米劇作家の “Things We Worried About When I Was Ten” という作品。若手の作家だろうと思って読み進めていたら、米中西部で育った彼が子どもの頃に夢中になった野趣あふれる遊びや地域の風習、小学校の授業風景などが出てきて、あれ、これは私の少年時代と似てなくもない。それでネットで作家の名前を検索すると、1940年生まれとある。私より一世代上の世代だが、凄く「感情移入」できる作品だった。
主人公の少年Danny Matzの友人、Jackieは同級生たちの不幸を一人で背負い込んだような幸薄い少年だった。家庭環境にも恵まれず、4歳で母親を亡くし、継母が来る。父親や継母から虐げられる日々。ある日、継母が台所で肉挽き器を操作していて、誤って親指を切断してしまう。これを目撃したJackie少年は近所中を駆け回り、 “Stepmom May cut her thumb off in the meat grinder” と大声で触れ回る。
Danny少年は最初、Jackieがなぜ狂ったように継母の不運を触れ回っているのか理解できなかったが、やがて腑に落ちる。継母が自分の親指さえ切り落とすことをしでかすなら、所詮赤の他人に過ぎない僕にはどんなことをするだろうか。僕もそのうち肉挽き器に詰め込まれてしまうことになるのかと恐れおののいているのだ。それで近所の人たちに自分がどういう「危機」に直面しているかを「告知」しておきたかったのだと。
兄弟のような近しい民族のウクライナの人々をさえ情け容赦なく蹂躙するプーチン大統領。ただでさえ疎遠な関係の日本もJackieのようにロシアの蛮行を国際社会に喧伝する必要がある。もっとも、国際社会はすでにそれは十分承知しているが・・・。
- Comments: 2
ウクライナ緊迫!
- 2022-03-01 (Tue)
- 総合
ウクライナ情勢。幼い子供がロシア軍のロケット攻撃で死亡したニュースなどを目にすると、胸が締め付けられるようで何とも陰鬱な思いに沈む。数日前かのこのブログで第二の冷戦のスタートかと書いたような気がするが、それどころか第三次大戦の勃発さえ危惧される事態だ。挙げ句の果てはロシア軍による核兵器の使用さえ懸念される。時代は21世紀。戦争の世紀は過ぎ去った20世紀のことではなかったか。
ウクライナの人々の苦難を思いやると拙ブログをアップデートする気など失せてしまう。とはいえ、このブログは私にとって備忘録でもあるのだから、きちんとその時々の思いを記しておきたい。数年後に振り返った時に、ああそんなこともあったな、懐かしいなあとほのぼのと振り返りたいが、今のウクライナ情勢はとてもそういう心境にはなれないだろう。ウクライナ、ロシアの和平交渉が奇跡的に進展することを心から願いたい。そしていつか、プーチン大統領が無垢の市民の尊厳を踏みにじった蛮行で歴史的に断罪されることを願う。
◇
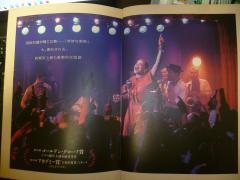 オンラインで細やかに実施している毎月2回の英語教室「短篇小説を読む」で最近取り上げたのは、“Endangered Species: Case 47401”という短篇。タイトルは物々しいが、米国に暮らす黒人女性が転居した白人住民多数派のコミュニティーで感じるようになった違和感がテーマとなった作品。私はそうした違和感が理解できるとまでは言わないが、南アフリカの白人至上主義の究極的なアパルトヘイト(人種隔離政策)の終焉を現場で取材した身としては興味深く読んだ。
オンラインで細やかに実施している毎月2回の英語教室「短篇小説を読む」で最近取り上げたのは、“Endangered Species: Case 47401”という短篇。タイトルは物々しいが、米国に暮らす黒人女性が転居した白人住民多数派のコミュニティーで感じるようになった違和感がテーマとなった作品。私はそうした違和感が理解できるとまでは言わないが、南アフリカの白人至上主義の究極的なアパルトヘイト(人種隔離政策)の終焉を現場で取材した身としては興味深く読んだ。
作品の中に Billie Holiday という人名が出てきた。ジャズに明るい人なら知っている人だろうが、私は正直、男かな?と思ったほどの門外漢。ネットで調べて、1930―50年代、アメリカを代表する女性ジャズ歌手であることが分かった。麻薬に手を染めていたこともあったらしいが、米政府を相手に人種差別の非を敢然と問うた勇気ある先駆者であることも。1959年に44歳の若さで病没している。公民権運動の嵐が吹き荒れ、キング牧師があの有名な “I have a dream.” の演説を残す4年前だ。
ネットでこの人物のことをチェックしていたら、今、福岡・天神の映画館で彼女の半生を描いた作品がかかっていることを知った。“The United States vs. Billie Holliday” というタイトルの映画。タイトルからして凄い!
先週末、映画館に足を運び、その映画を観た。セックスシーン、麻薬、暴力、リンチの凄惨なシーンも盛り込まれており、気安く推奨し難い点もあったが、あの国が抱えている人種問題が如実に描かれていた。彼女が米政府から忌み嫌われたのは “Strange Fruit” (奇妙な果実)と呼ばれる歌をステージで歌わないよう迫られても、それを拒絶したこと。南部では奇妙な果物が木からぶら下がっていると歌われた果物とは何か? 白人至上主義者グループのリンチに遭い、木から吊される黒人の亡骸のことだ。
作品の中では今では絶対タブーの黒人蔑視の表現が頻出する。黒人同士がお互いを罵る時にも口にする。このブログで紹介する分には差し支えないないだろう。 “Fuck you, nigger!” 今アメリカでこのような暴言を吐いたなら、即アウトだろう! いやどこであれ。
- Comments: 0
寒い!
- 2022-02-23 (Wed)
- 総合
中国語を学ぶ喜び、楽しみは多々あるが、我々が小さい頃から親しんできた諺や成句を改めて知ることもその一つだろうか。我々が日常的に使っているそうした表現が中国語では若干異なることを知った時には興味は倍加する。
最近の例を一つ。朝三暮四。中学か高校の国語(?)の授業で出てきたかと思う。広辞苑には①「目前の違いにばかりこだわって、同じ結果となるのに気がつかないこと②口先でうまく人をだますことと載っている。私は①の意味で記憶している。中国語の辞書を引くと若干異なるようだ。「貶(けな)す語」として紹介されており「変転きわまりない、ころころ変わる」という意味が記してある。ネットで調べると「移り気である、考えや方針が定まらず、当てにならない」というのも出てきた。「信用に値しない」ということか。
五十歩百歩。たいして違いがないことを言う時に使うが、これは日中で意味合いに差異はないようだ。本家の中国では「五十歩笑百歩」と「笑う」という字が間に入る。「笑」が入って意味がより明確になるような気もする。戦で50歩逃げた兵が100歩逃げた兵を臆病だと笑う資格がないことはもっともなことだ。
◇
ウクライナ情勢が緊迫の一途にあるようだ。民族的には親戚のような東スラブ民族同士のいがみ合い。ロシアとの関係より欧米との関係緊密化を選択したウクライナに非はないように思えるが、ウクライナは本来、ロシアゆかりの地と見なすプーチン大統領にとっては座視できないことなのだろう。
ネットで購読している米高級誌ニューヨーカーのウクライナ関連の記事を読んでいて、興味深いものがあった。見出しにひかれた。”Inside the high-stakes fight to control the narrative on Ukraine” バイデン米大統領はこのところ再三、プーチン露大統領がウクライナ侵攻を既に決定と非難しており、ロシアに対する厳しい経済制裁の発動も表明している。プーチン大統領はウクライナ東部に兵を進めるのはウクライナの親露派勢力に対する攻撃への自衛措置であり、侵攻ではなく平和維持が目的と主張している。どちらの物語(narrative)すなわち言い分が正しいのか。国際社会には自明の理のように思えるが、現実に戦争状態となり、ウクライナの無垢の市民が殺傷され、いわんや、第三次大戦を招来することにならないよう祈りたい。
◇
このところ寒い日が続いている。火曜日、仕事で小倉に向かったが、かじかむような冷たい風に見舞われた。地球温暖化とは相容れない厳寒のようにも思えたが、北日本各地が見舞われている豪雪もこの寒さも温暖化に起因している気象の一つでないことを祈りたい。
早く春の到来が待たれるが、春が来れば、日米でまた球春開幕となる。テレビやパソコン、スマホの画面に向き合う時間がいよいよ増える。中国語、韓国語の学習に割く時間は激減する定めだ。今は午前中だけは机に向かうようにしているが、大リーグのオープン戦が始まればそれも危うい。何かいい手を思いつかなくては。テレビだけでも廃棄処分にすればほぼ問題は解決するのだが・・・。
- Comments: 0
温故知新
- 2022-02-17 (Thu)
- 総合
冬季五輪。日本の金メダルは2個。これも金メダルは確実なんだろうなあと思いながら、仕事帰りの電車の中でスマホのNHKラジオの生中継に耳を傾けていた。団体追い抜きと呼ばれる女子パシュートだ。テレビで見ていると、しのぎを削る2つのチームの速い、遅いが画面から手にとるように分かる面白い競技だ。決勝の相手はカナダチーム。日本チームは連覇がかかっている優勝候補だから、安心して聴いていた。
期待通り終始カナダを抑え、リードを奪っていた。3個目の金メダルだなと思っていたら、最後のコーナーであろうことか、最後尾を滑っていた選手が転倒した(ようだ)。解説の女性が何か叫んでいるが、いずれにしろ、転倒してしまっては逆転負けだ。ラジオ放送だけに詳しい事情は分からない。解説者は遅れていたカナダチームが迫ってきてはいるが、最後尾の選手はフォームが乱れ始めているようなことを言っており、まあ、大丈夫だろうと思っていた矢先の転倒!
解説者も男性アナも連覇がならず、銀メダルに終わったとはいえ素晴らしい成績であり、祝福したいとかなんとかしゃべっている。その通りではあろうが、何とも後味が悪い。敗色濃厚の中での転倒だったら、諦めもつくだろうが・・・。
◇
毎月第1,3水曜日の午後、小倉駅前のビルで行っている英語教室。受講生は一人だが、英会話の基礎から文法まで楽しく教えながら学んでもいる。昨日の教室が終わった後、受講生が古びた中国の新聞をくれた。以前に中国を旅行した時に持ち帰ったとか。私が中国語を学んでいるので、役に立つかと思い、持って来て頂いたようだ。
現地発行の英字新聞も含まれていた。「CHINA DAILY 中国日報」。日付を見ると2009年12月19日。13年前の新聞だ。ネットで検索すると、この新聞は中国共産党中央宣伝部が保有する英字日刊紙と紹介されている。パラパラと紙面をめくってみた。一面はオバマ米大統領(当時)と中国の温家宝首相(同)がコペンハーゲンでの地球温暖化問題を討議する国連の会議に出席した際に二人だけで会談している写真が掲載されている。
興味深く読んだのは社説と思われる欄で、上海の大学院で学ぶ女性の院生が自死したことを憂える記事だった。詳しい事情はこの記事だけではうかがい知ることはできないが、貧しい母子家庭で育った彼女は大学卒業後も希望する仕事に就くことができず、7年経過して大学院で更に学ぶことを決意。退職した母親はどうやら娘がただ一人の頼りだったようで、彼女は大学の寮に母親も呼んで一緒に暮らすことを望んだ。しかし、大学側にこれを拒絶され、絶望の果てに自死を選択したようだ。次の一節、何度も読み返した。
Had the university showed enough concern for the difficulties this student faced, she would not have chosen to end her life. Now, universities and other sectors should try to do something to help those on the verge of being reduced to sheer despair before it is too late.(大学がこの学生が直面していた困難に十分配慮していたなら、彼女は自死を選択していなかっただろう。諸大学や関係する当局は事態が収拾不可能になる前に絶望の極に瀕しつつある若者に助けの手を差し伸べるべきだ)。この訴えが今も息づいていることを祈りたい。
- Comments: 0
第二の冷戦の始まり?
- 2022-02-12 (Sat)
- 総合
依然、勢いの衰えないコロナウイルス。3回目の接種を受けた。前2回とは異なるワクチンゆえ、ちょっと不安は感じたが、待ち時間もあまりなく、スムーズに接種は終わった。これが最後になればいいのだが、また今年後半に4回目の接種を受けていたりして・・。まあ、そんな事態には至らず、今のコロナ禍もほどなく終焉することを祈ろう。
それはそれとして、接種翌日に微熱が出た。体温を測ると36.5度。多くの人には平熱だろうが、私は平熱が35.7度の冷血種族。少し気になった。だが食欲はあるし、身体に違和感もない。ワクチン接種に起因しているとは思えない。私は寝相が悪く、いつもベッドの毛布、布団を蹴散らして寝入っている。それで明け方に寒さで目覚めることがある。睡眠不足がたたり、風邪の症状を呈したのだろうと思った。それでもさすがに気になるので、薬局で葛根湯を買い求め、体調回復を祈った。
今、こうしてラップトップに向かっていて、体温も体調もほぼ平常に戻ったように感じている。健康のありがたみを改めて感じた次第。
◇
北京冬季五輪。九州に住んでいると、ウインタースポーツには縁遠くなる。新聞社の盛岡支局に勤務していた頃は同僚と一緒に、時には一人でスキー場に行き、初めてのスキーを楽しんだ。最後までボーゲンで滑るのが精一杯だったものの。スキーの後は帰途に温泉に寄るのが定番だったが、それも遠い過去の話。思い出すこともあまりない。
冬季五輪にはそうは興味はないが、見始めるとやはり熱くならざるを得ない。女子カーリングにしてもそうだ。序盤の戦術的なことは正直よく分からないが、ストーンと呼ばれるものを繊細なタッチで氷上の目指した地点にきちんと置くのが至難の業であることは容易に分かる。土曜日のデンマーク戦の土壇場での逆転勝利は実に見応えのある一戦だった。ひょっとして全国でカーリングをプレーする人口が増えたりして・・。
◇
日本から遠く離れているが、ウクライナ情勢が緊迫の一途にあるようだ。私はウクライナでは取材経験はないのでよく分からないが、冷戦時代にはソ連の統治下にあった国でロシアに対する親近感を抱く人々も少なくないのだろう。そうした無垢の人々にロシア軍が銃火を向ける最悪の事態になることのないよう祈りたいが、彼らの命運がプーチン・ロシア大統領の胸三寸にあるとしたなら、あまり期待しない方がいいように思える。
ネットで定期購読している米高級誌ニューヨーカーでは、このウクライナ情勢に関して「ロシアと中国が米国その他の国々に対して事実上の同盟関係を構築している」と題したコラム記事を掲載していた。その中で執筆者はロシアはウクライナ、中国は台湾へのそれぞれ侵攻が懸念される中で、プーチン大統領が冬季五輪の開会式に合わせて訪中し、習近平国家主席と首脳会談を行い、共同声明を発表したのは象徴的な出来事であり、将来、我々はこの会談を「第二の冷戦の始まり」(the beginning of the Cold War Two)と振り返ることになるのかもしれないと解説している。第一の冷戦が終結したのはベルリンの壁崩壊直後の1989年12月。それから30余年経過してまた新しい冷戦がスタートするのだろうか。
- Comments: 0
韓国語ドラマに丸一日はまる!
- 2022-02-09 (Wed)
- 総合
前回の項で中国語教室で教わった「中国国乒谁也赢不了 中国国足谁也赢不了」という文章を紹介した。中国の人々が中国が誇る男女卓球(国乒)と不振の男子サッカー(国足)を自虐的に比較した対句だった。「谁也赢不了」(誰も勝てない)という述語が同じで、普通、日本語の文章ではあり得ない構文だと思うと書いた。その上で「中国卓球にはどの国も勝てないが、中国サッカーもどの国にも勝てない」と解釈すべきなのだろうと。
念のため、新聞社勤務時代の後輩で中国語に明るいM君に尋ねた。M君は概ね私の解釈でいいでしょうと言ってくれた。とりあえず安心。要するに中国人であれば、女子でもそうだが、男子卓球では中国を脅かす国は存在しないこと、これに対し、男子サッカーに関しては中国は日本を含めた他国に大きく遅れを取っていることを誰でも承知しているので、上記の解釈が自然だということらしい。
これをもって中国語はずいぶん大雑把な言語だと考えるのか、おおらかな言語だととらえるのかは人それぞれだろう。私は後者の立場を取りたい。英語を学んでいると、この文章の主語は何?述語は何?目的語は何?などとこだわりたくなるが、中国語ではあまりそうこだわる必要はないのかなと(個人的に)思っている。それに上記の文章では最初に登場する「中国国乒」と「中国国足」は主語ではなく、おそらく主題(テーマ)なのだろう。日本語で言う「象は鼻が長い」という文章で、主語は「鼻」であり、最初の「象」はこの文章の主題と呼ぶのと同じだ。そう考えれば、分かりやすいのではないかと思う・・。
◇
以前に書いたことがあるかと思うが、韓国語のドラマははまりやすいのであまり見ないようになって久しい。時々、つまみ食いしては沼にはまりそうになっていることも。
数日前の日曜日。どつぼにはまってしまった。たまたまパソコンで無料のAbemaTVのチャンネルをスクロールしていたら、韓国語の連続ドラマを放送していた。私の好きな女優さんの顔が映ったので、韓国語の勉強にちょこっとだけ見ようと考えた。気がついたら数時間が経過していた。もうやめようと思ったが、なかなかできない。結局午後1時半ごろから夜の10時までずっと見る羽目になった。その間、トイレに立っただけ。空腹も我慢した。
全22話のドラマを2日に分けて、それぞれ11話をぶっ続けで放送したようだ。私は後半の13話かそこら辺りから見たことになるのか。とにかく、韓国語ドラマはベタな内容が多いので言葉の勉強という「大義名分」がなければ遠慮したいのだが、正直言って面白い。かてて加えて女優さんに魅力的な人が多く、魅せられて、そして見せられてしまう。
3組のカップルが登場したが、メインのカップルは契約結婚したものの、お互いのことをあまり知らず、交わす言葉は敬意を示す丁寧な表現。比較的ゆっくり語りかけていたので聞き取りやすかった。いろいろと勉強になった(気がしている)。一つだけ、ぼんやりと覚えているのは成人した大人であっても両親にはきちんとした(絶対)敬語を使っていたこと。まあ、日本ではとっくに消え去ったしきたりだろう。接客業の可愛い女性が出勤前に韓国語で「アイウエオ」(?)と発声して仕事モードに入っていたことも印象に残っている。韓国語がまるで日本語であるかのような錯覚に陥った。
- Comments: 0
生姜ほうじ茶
- 2022-02-04 (Fri)
- 総合
 拙文いや節分、立春ときて、私は68歳の誕生日を迎える。70代突入が目前だ。早生まれでない同級生は60代最後の一年か。「人生七掛け論」を信奉する私は、70代は昔の50代、これからが脂の乗った人生が始まるのだと言い続けているが、自分がその年代に差し掛かろうとしている今、少し弱気になっているのも隠せない。
拙文いや節分、立春ときて、私は68歳の誕生日を迎える。70代突入が目前だ。早生まれでない同級生は60代最後の一年か。「人生七掛け論」を信奉する私は、70代は昔の50代、これからが脂の乗った人生が始まるのだと言い続けているが、自分がその年代に差し掛かろうとしている今、少し弱気になっているのも隠せない。
とまあそれはともかく、来週、3回目のコロナワクチンを接種することになった。ファイザー、ファイザーの次はモデルナ。モデルナは評判があまり芳しくないとも聞くが、3回目は別のワクチンの方が効果がアップするとも言われているとか。こっちの方を信じよう。
コロナ対策でマスク、うがい、手洗いを励行しているのが功を奏してか分からないが、この2年以上、風邪を引いていない。毎年2,3回は風邪を引いている私としては画期的な出来事。最近はコロナにも効くとかの風聞もある生姜茶を愛飲し始めた。らっきょう酢漬けの野菜ピクルスに納豆、生姜茶で健康で実りある長寿を謳歌したいと願っている。
◇
風邪引きベテランの私は風邪を引く「端緒」はすぐに察しがつく。必ず喉の痛みが先にやって来る。あ、喉がなんだかおかしいと感じたら、ほどなく熱が出てくる。扁桃腺が弱いのだろうか。何しろ、平熱が35.7度ほどの身体だ。36度半ばを超すと怖い。37度に達すると焦る。
先日、英語教室で足を運んだ小倉駅ビルのお茶屋さんの前を通りかかったら、生姜茶を試飲させていた。私は本来、生姜が好きで、一頃は味噌汁の中にも放り込んで食していた。今はさすがにしないが、八百屋の店頭に置いてあるとつい買ってしまう。
買い求めたのは「生姜の深炒りほうじ茶」。熱湯を注いで飲むと生姜の香りがして旨い。蜂蜜を垂らすと甘さが出て更に味わいが引き立つ。ネットで調べてみると、コロナ禍で生姜茶が脚光を浴びているとか。ますます意を強くした。らっきょう酢にゴーヤや牛蒡、にんじん、タマネギなどの野菜を漬けてピクルスにして食べるようになって久しい。人様には「私の健康はらっきょう酢の野菜ピクルスのお陰です」と言ってきたが、これからは野菜ピクルスに生姜茶を加えることになりそうだ。生姜茶は英語では ginger tea とか。
◇
公民館の中国語講座。老师(先生)がプリントアウトを配布した。ワールドカップを目指す男子サッカーの試合で中国チームはベトナムに1対3で敗れ、ワールドカップ出場の可能性は潰えた。中国のサッカーファンは怒り、嘆き、悲痛の涙を流していることがユーモラスに綴られていた。
その中で以下の対句が出てきて、私を含めた受講生諸氏は面食らってしまった。「中国国乒谁也赢不了 中国国足谁也赢不了」。中国が誇る卓球(国乒)と不振のサッカー(国足)が皮肉たっぷりに比較されている。「谁也赢不了」(誰も勝てない)という述語は全く同じ。普通、日本語の文章ではあり得ない構成だと思う。「中国卓球にはどの国も勝てないが、中国サッカーもどの国にも勝てない」と解釈すべきなのだろうか。自宅に戻ってあれこれ考えて、ようやく意味合いが分かった(気がした)。
- Comments: 0










