May 2012
ダニエル・デフォー(Daniel Defoe) ④
- 2012-05-31 (Thu)
- 総合
ロビンソンはかくして1686年12月19日に無人島を後にする。28年と2か月、19日の歳月を島で過ごしたことになると述べられている。イングランドには翌年の1687年6月11日に到着。35年ぶりの母国への帰還だった。
主人公はその後、ブラジルに残していたプランテーションの「権利」が認められ、ほどなく、5000ポンドの財産を有する金持ちとなる。当時としては莫大な資産だったのだろう。プランテーション自体、年間1000ポンド以上の収益を見込むことができた。彼はその後、かつて自分を救ってくれたポルトガルの老船長ら恩義のある人々に相応以上のお返しをして、イングランドに落ち着き、結婚して3人の子供をもうける。自分の甥にあたる若者二人の面倒も見て、このうちの一人を立派な船乗りに育て上げる。普通ならこの辺りで物語は大団円となるのであろうが、妻に先立たれたことや、生来の旅好きから、船乗りとなった甥の勧めもあり、1694年、貿易商として今度は英国が権益を持っていた東インド諸島への航海に出る。主人公は1632年の生まれとあるから、62歳となっているはずだ。今ならまだ老け込む年ではないが、当時としては古老の域に差しかかる年齢だったのではないか。

この小説はデフォーのあくまで創作であると伝えられている。私はこの小説を読みながら、作家吉村昭の書いた記録小説『漂流』(1976年)も想起していた。こちらは江戸時代、文字通り絶海の無人島に漂着した土佐の一人の船乗りの物語で、不毛の島で12年間、島に飛来するアホウドリを主食に、雨水で生き長らえる壮絶な物語だ。主人公の船乗り、長平の生への執着、故郷の土を再び踏むのだという執念に胸を打たれたが、私の記憶に間違いがなければ、ロビンソンとは異なり、神や神的存在との「問答」はあまりなかったかと思う。日英の「お国柄」が垣間見えると感じた。
デフォーは序文でこの物語は“the Wisdom of Providence” (神の摂理の導き)への賛美であると述べている。“Robinson Crusoe” が奴隷貿易を背景にした物語であることを忘れてはならないだろうが、この物語が信仰や美徳の大切さを訴えた寓話にとどまらず、今なお世界中の読者を引きつけるのは物語の理屈を超えた面白さゆえだろう。なるほど、「英国最初の小説」とも称されるのは納得できる。
なお、アメリカの大学教授、デイビッド・ハケット・フィッシャー氏が1989年に刊行した歴史書 “Albion’s Seed” という本によると、イングランドで ”class” という言葉を使用した最初の人物はデフォーであり、彼は1705年にはすでに現代の我々が使っている意味で ”class” という言葉を使用していると指摘している。デフォーは当時すでに、イングランドの社会を「豊かさ」によって七つに区分しているという。それを読むと、現代でも何ら変わりがないことに驚かされる。アメリカでもそうだったが、英国のメディアではこうした貧富の差を憂えるニュースが今も絶えない。
デフォーの区分は「つづき」で。私は③から⑤いや⑥になりつつあるかもしれない。
(写真は、連日の爽やかな好天でパブは夕刻ともなると酒を楽しむ長蛇の人々)
ダニエル・デフォー(Daniel Defoe) ③
- 2012-05-30 (Wed)
- 総合
主人公が流れ着いたのは無人島ではあるが、絶海の孤島ではなかった。時に、近くの島々に住む人食い人種の蛮人が到来していた。戦いで捕虜にした敵対する部族の人間をこの無人島に連行して殺害、その人肉を焼いて、貪り食っているのだ。
主人公は恐怖に怯える。と同時に、蛮人を殺害することには抵抗を覚える。この辺りは読んでいて共感した部分だ。彼は考える。蛮人が同じ人間を食べることは理解できないし、許されざる行為として激しい怒りを感じるものの、それは彼らの風習であり、自分に現時点では危害を加えていない彼らを私は何の権利があって殺害するのであろうか。それでは自分も「殺人鬼」となるのではないか。しかし、彼らに見つかれば、自分が殺され、食われるのは必定であり、彼らを殺害することは自己防衛(self-preservation)に過ぎない。さらに、彼らが食おうとしている捕虜を助け、味方とすることで無人島生活からの脱却につながる可能性が見つかるかもしれない。このような心境に至った主人公は人食い人種と次に遭遇したならば、彼らと敢然と戦うことを決意する。

無人島に住むようになって27年の歳月が流れた。この間、人食い人種の男たちに食われる寸前だった蛮人の男やスペイン人の船乗りたちを助け出し、島の人口は主人公を含め4人に増えた。そうした折、イギリス人が乗り込んだ船が船員の反乱で無人島の沖合まで漂着。主人公は生命の危機にあった船長ら3人を助け出し、船員の反乱を収拾させたことで、無人島から脱却する絶好の機会に巡り合う。窮地を救ってくれたことに感謝する船長に向かい、彼は神が自分たちにこういう機会を与えてくださったのだと語る。
I told him I looked upon him as a man sent by Heaven to deliver me, and that the whole transaction seemed to be a chain of wonders; that such things as these were the testimonies we had of a secret hand of Providence governing the world, and an evidence that the eye of an infinite Power could search into the remotest corner of the world, and send help to the miserable whenever He pleased. I forgot not to lift up my heart in thankfulness to Heaven; and what heart could forbear to bless Him, who had not only in a miraculous manner provided for me in such a wilderness, and in such a desolate condition, but from whom every deliverance must always be acknowledged to proceed.(私は船長に言った。あなたは神が私を救い出すために送ってくれた人間であると思うと。船が到来して以来の一連の経過は驚きの連続であり、それはまた神がこの世を統治していること、神の無限の力は世界の果ての果てまで及んでおり、神がそう望めば、悲惨な境地にある者にいつでも助けの手を差し伸べることができることを証明するものだとも。私は同時に神に感謝することも怠らなかった。時ここに至って、神を賛美することを控えることができる者など誰がいようか。神はこのような荒れ地で、しかも絶望的な状況下で私を奇跡的に生き長らえさせ、そして今、私がこの島から抜け出す機会を与えて下さろうとしているのだ)
(写真は、大英博物館は昔も今もいつ行っても観光客でいつもの賑わい)
ダニエル・デフォー(Daniel Defoe) ②
- 2012-05-29 (Tue)
- 総合
ロビンソンは結局流れ着いた南米のブラジルで農園経営に乗り出し、成功を収める。そして当時盛んになりつつあった奴隷貿易に目をつけ、自らアフリカに奴隷を買い付けに行くことを企図する。だが、航海の途中、嵐に遭い、自分一人だけ命は助かったものの、無人島に流される。小説では1659年、主人公が27歳の時とされている。
北米に目を転じれば、英国からアメリカに向け、新天地を求める人々の移住が進み始めていた時代だ。それとともに、新天地で綿花やタバコを栽培する強健な労働力としてアフリカの黒人が奴隷貿易の餌食となっていった。ロビンソンも奴隷貿易に参画して富を蓄えることに良心の呵責は何ら覚えない。
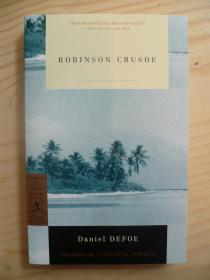
無人島での生活を余儀なくされて、彼は初期のころは次のような思いに至る。
Upon the whole, here was an undoubted testimony that there was scarce any condition in the world so miserable but there was something negative or something positive to be thankful for in it; and let this stand as a direction from the experience of the most miserable of all conditions in this world: that we may always find in it something to comfort ourselves from, and to set, in the description of good and evil, on the credit side of the account. (全体から見て、私が経験していることはこの世の中に悲惨極まりないという状況などめったにあるものではないということの紛れもない証明だ。そうした悲惨な状況であっても、否定的なものだけでなく、感謝すべき何かしら肯定的なものがあるものだ。このことを、私がこの世で最も悲惨な状況を味わった経験を通して得た教訓として生かして欲しい。どのような状況の中でも何かしら慰められるものが見出されるものであり、物事の善と悪で言えば、善として見なされるべきものだ)
だが、無人島での寂しい生活、不便この上ない生活が長引くにつれ、彼の気持ちは当然のことながら折れそうになる。そうした主人公を支えるのはそれまでは意識することのなかった信仰だ。聖書及びキリスト教の信仰だ。
These reflections made me very sensible of the goodness of Providence to me, and very thankful for my present condition, with all its hardships and misfortunes; and this part also I cannot but recommend to the reflection of those who are apt, in their misery, to say, “Is any affliction like mine?” Let them consider how much worse the cases of some people are, and their case might have been, if Providence had thought fit.(私はいろいろ考えた末に、神の摂理が私に施してくれた善意に気づき、さらには確かに困難、不運はあったものの、現在の境遇に深く感謝の念を覚えるようになっていった。この点に関して、不幸な境遇にある人々が「自分のように苦しんでいる人が他にあるだろうか」と嘆いているとしたら、私は次のように忠告したい。もし神があなた方がそれにふさわしいと考えたとしたなら、あなた方は今よりさらに厳しい境遇に置かれていたことであろうということを肝に銘じておくべきだと)
(写真は、ロンドンで購入した “Robinson Crusoe”。価格は5.99ポンド[約840円] )
ダニエル・デフォー(Daniel Defoe) ①
- 2012-05-28 (Mon)
- 総合
デフォーは17世紀中葉から18世紀にかけて生きた作家で、その代表作 “Robinson Crusoe” はイギリス近代小説の先駆者とされる作品だ。1719年に刊行されている。私は「ロビンソン・クルーソー」の名前ぐらいは知っていた。「無人島に流れ着いた男が艱難辛苦の末に母国に帰還する」物語ぐらいの知識も。今回の旅を前に実際に小説を読んでみて、その面白さに引き込まれた。
書き出しから興味深い。語り手の「私」は1632年にイングランド北部のYorkで謹厳実直な商家の三男坊に生まれたことが明らかにされる。父親は「私」に法律の世界で生きるよう教育の機会を与えてくれたが、「私」は船乗りになる道を選ぶ。やがて、カリブ海の孤島で28年に及ぶ無人島生活を余儀なくされる運命が待っているとは露知らず。
父親は外の世界が見たくてたまらない息子を概ね次のように言って諭す。「お前は中流階級の人間なのだ。下層階級の中の上流層と呼べる階層とも言える。私は長い経験から、我々の階層こそが世の中で一番暮らしやすい階級であることを知っている。職工の階層で生きる人々のような悲惨で困窮した生活からは無縁であり、上流階層の人々が味わう高慢や野心、嫉妬に悩まされることもない。歴代の王様だって、我々中流階級の人間に生まれてきたかったと嘆いているほどなのだ。貧困もなければ富もない、真の幸福を享受できる階層なのだ」(He told me that mine was the middle State, or what might be called the upper Station of Low Life, which he had found by long Experience was the best State in the World, the most suited to human Happiness, not exposed to the Miseries and Hardships, the Labour and Sufferings of the mechanic Part of Mankind, and not embarass’d with the Pride, Luxury, Ambition and Envy of the upper Part of Mankind….That this was the State of Life which all other People envied, that Kings have frequently lamented the miserable Consequences of being born to great things, and wish’d they had been placed in the Middle of the two Extremes, between the Mean and the Great; that the wise Man gave his Testimony to this as the just Standard of true Felicity, when he prayed to have neither Poverty or Riches.)

この小説が刊行されたころ、日本は江戸時代。「士農工商」の封建制度の時代だ。日本では「商」の世界に生きた当時の人々が「士農工」特に「士」の人々に対して上記のような「達観」に浸ることなど到底できなかったことだろうと思いを馳せた。もっとも、江戸時代の庶民がどのような暮らしをしていたかなど私は定かには知らない。「荒野の素浪人」や「水戸黄門」などかつて良く見たテレビドラマから「想像」しているに過ぎない。
それはそれとして、ロビンソン・クルーソーの両親が「堅実に生きなさい」と「私」を諭すくだりは、古今東西、中高年層の読者には思い当たる節があるのではなかろうか。私もこのくだりで手がしばしとまった。
(写真は、27日の「サンデー・タイムズ」の雑誌のエリザベス女王の即位60周年を祝う特集記事。前項のコメントの質問にタイミングの良い見出しが。「つづき」で)
ジョージ・オーウェルとお茶
- 2012-05-26 (Sat)
- 総合
ロンドンに到着して最初に投宿した民家の屋根裏部屋を「脱出」して、今はそう遠くないきちんとしたホテルに住まっている。一泊45ポンド(約6300円)。ロンドンではとてもリーズナブルな値だと思う。それに朝食付きだ。ネットで例によって「ガチャガチャ」(悪戦苦闘の私なりの擬音語)やっていて見つけたホテルだ。
Fountain House Hotel という名の実質的にはB&B(ベッド&ブレックファースト)のようなホテルだ。最初の民家から近く移動が楽だったことと安かったことのほかに、ここに決めたのはもう一つ理由があった。このホテルがあの文豪、ジョージ・オーウェルゆかりの深い宿であることを知ったからだ。

このホテルはかつて14人の生徒が学ぶ小さな高校だった。オーウェルは1932年から一年余、ここで「住込み」で教壇に立っていたという。食堂がある母屋の建物は当時のままで、食堂の壁に当時の白黒写真が一枚飾られている。数日前、朝食を食べていたら、経営者のマダムが「あなたはオーウェルに関心がおありそうだわね。彼はこんな文章も書いているのよ。読んでみる?」と一枚の紙をくれるではないか。
“George Orwell’s Perfect Tea” という表題の文章のコピーだ。「ジョージ・オーウェルの完璧のお茶」。何やら面白そうではないかいな。イングランドでお茶を飲むならかくあるべしという11か条をうたった、いわば「オーウェルお茶の11戒」だった。1946年にロンドンの夕刊紙に寄稿した文章らしい。
最初に、お茶はインドやセイロン(スリランカ)の茶葉に限るとしている。中国の茶葉も悪くない。ミルクなしで飲める経済的なお茶だが、難点は中国茶はいくら飲んでも「知恵も勇気も元気」も出てこないと皮肉っている。ティーポットはお湯で洗って温めるよりも直に温めておくべしとか、お湯が沸いたら、その熱湯を茶葉を入れたティーポットに即座にそそぐべしとか、興味深い「戒め」が列記されている。
我が意を得たりと思ったのは、最後の11番目に書かれた「戒め」だ。お茶に絶対砂糖を入れてはならない。砂糖を入れることによってお茶のflavour(風味)が損なわれる。それでどうしてあなたはお茶の愛好家と自分を呼ぶことができるのかと作家はたしなめている。私はお茶もコーヒーも砂糖抜きで飲むからこの「戒め」には賛同できる。作家はさらに言う。「お茶に塩やコショウを入れて飲むのはリーズナブル。そもそもお茶はbitter(苦い)なものである」と。これは果たして額面通りに受け取っていいものか、私には分からない。ここ数日、試しに朝食のテーブルでお茶にコショウをかけて飲んでいる。味は?確かにコショウの味がほのかにする味わいだ。
オーウェルにとっては日本茶(緑茶)も中国茶と同じ範疇なのだろう。深夜に宮崎(米良)の幼馴染が餞別代わりにくれた、彼が作った田舎の緑茶をしみじみ飲んでいる。「知恵」や「勇気」は得られなくとも「癒し」は得られている。作家にぜひ伝えたかった風味だ。
(写真は、ホテル食堂に飾られている写真。右端の男性がオーウェル)
“George Orwell’s Perfect Tea” 原文は「つづき」でどうぞ。
アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)④
- 2012-05-25 (Fri)
- 総合
著者のドイル卿は1859年にスコットランドのエディンバラに生まれ、1930年に没している。父親はアルコール中毒だったが、愛情豊かな母親が語って聞かせる物語に胸をときめかせて育った少年だった。大学で医学を専攻し、医者として開業した後、作家に転身。医学を学んだことが推理小説のプロットを導き出すのに大いに役立ったようだ。

Sir Arthur Conan Doyle Literary Estateのオフィシャル・ウエブサイトに掲載されている伝記を読むと、約70年の人生で多くの推理小説や戯曲を刊行して成功を収める一方、戦争にも従軍し、政治の世界にも挑んだりと波乱に富んだ人生を送ったことが分かる。
しかし、彼の名を不朽のものにしたのは1891年7月から翌年にかけて雑誌連載された “The Adventures of Sherlock Holmes” の12編の作品だったことは改めて言うまでもないだろう。ホームズは “A Study in Scarlet” の中でワトソンに事件の捜査に当たっては “reasoning backwards”(時系列を逆転させて推理すること)が大切なことだと語る。
“Most people, if you describe a train of events to them, will tell you what the result would be. They can put those events together in their minds, and argue from them that something will come to pass. There are few people, who, if you told them a result, would be able to evolve from their own inner consciousness what the steps were which led up to that result. This power is what I mean when I talk of reasoning backwards, or analytically.”(もし君が一連の出来事を説明したとしたなら、たいていの人々はその結果がどうなったかということを君に語ることだろう。彼らは頭の中でそうした出来事を思い描き、その結果としてそうなるということを君に説明できるのだ。しかし、君がまず最初に結果だけを告げたとしたなら、その結果に至るまでどういうことが起きたであろうかということに思いを巡らせることができる人はほとんどいないだろう。この能力こそ、時系列を逆転して推理すること、あるいは分析的に推理することと私が呼んでいるものだ)

ロンドンで発生した不可解な連続殺人事件はホームズの見事な推理で解決する。しかし、ホームズの活躍は世間に知られることもなく、犯人逮捕後の新聞ではロンドン警視庁の刑事たちの有能さがたたえられた。この新聞は、事件が米国での怨恨に端を発した復讐劇だったことから次のように警告している。「英国を訪れる外国人はもしいさかいを抱えているのなら、英国の土を踏む前に解決してきた方がいい。いさかいが事件に発展すれば、我が国には優秀な捜査陣が待ち構えている」と。実際にはドイル卿の警告なのだが。
…it, at least, brings out in the most striking manner the efficiency of our detective police force, and will serve as a lesson to all foreigners that they will do wisely to settle their feuds at home, and not carry them on to British soil.
19世紀末、大英帝国として栄華を誇っていた英国の強烈なプライドが垣間見えるようだ。ドイル卿が今もホームズものを書いていたら、ロンドン五輪でこの国を大挙して訪れる海外からの来訪者にどういうメッセージを託すか知りたいものだ。
(写真は上が、24日のロンドンは29度と今年一番の暑さとなり、道行く人の装いも夏模様に。下は、中心部のレスタースクエア。改装工事が終了してこの日から一般開放された)
アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)③
- 2012-05-24 (Thu)
- 総合
ホームズは文学や哲学、天文学などについては暗かった。これに対して、化学、解剖学、地質学などの分野には明るく、専門的な知識を有していた。ワトソンはホームズが一体何の仕事をしているのかいぶかる。そして彼自身の口から彼が探偵業の仕事で糊口を凌いでいることを知る。

ホームズ曰く “I suppose I am the only one in the world. I’m a consulting detective, if you can understand what that is. Here in London we have lots of Government detectives and lots of private ones. When these fellows are at fault they come to me, and I manage to put them on the right scent.”(私のような仕事をしている者は世界で二人といないかと思う。私は探偵のコンサルタント業をしている。私の意味しているところが分かってもらえるだろうか。ここロンドンにはお役所に属している探偵が沢山いるし、民間で探偵業を営んでいるのも大勢いる。彼らが難問に直面した時に私のところにやって来るのだ。私は彼らの相談を受けて、問題解決につながる手がかりを見つけ出してやっているのだよ)
さて、物語はロンドンで発生した不思議な連続殺人事件を巡って展開する。ある夜、空き家になっていた住居でアメリカ人の男性旅行者が不審死しているのが見つかる。その直後、彼の連れの男性秘書もホテルの一室で殺されているのが見つかる。
ホームズはロンドン警視庁の刑事からいつものように支援要請を受け、現場に駆けつけ、残されていた足跡や結婚指輪などを手掛かりにこの難解な事件の解明に当たる。事件の背景には19世紀のアメリカ・ユタ州で隆盛となったモルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)の「暗部」が描かれていて、引き込まれて読んだ。

事件解決の有力な物証、証言を得たホームズは皆目見当がつかないワトソンに語りかける。書名の由来が出てくる場面だ。“…; a study in scarlet, eh? Why shouldn’t we use a little art jargon. There’s the scarlet thread of murder running through the colourless skein of life, and our duty is to unravel it, and isolate it, and expose every inch of it….”(「緋色を調べるのだよ。芸術用語を使わせてもらえればだ。一見無色の人生という名の織物をよく見れば、殺しの緋色の糸が絡んでいることもある。我々の責務はもつれた糸をほどき、仕分け、織られているあらゆる糸を明るみに出すことだ」)
犯人に目星を付けたホームズはロンドン警視庁の刑事に向かい、この事件に関してはこれ以上の殺しは起きないこと、自分には犯人が誰であるか分かっていること、間もなく犯人を捕らえて見せることなどを明らかにする。だが、逮捕の危機が迫っていることを犯人に気づかれたなら、彼を捕まえることは難しいことも。 “..; but if he had the slightest suspicion, he would change his name, and vanish in an instant among the four million inhabitants of this great city….” 。19世紀末にロンドンの人口はこの時すでに400万人の大都会であったことがここからうかがえる。
(写真は、シャーロック・ホームズ博物館を出ると、すぐ近くにあるのが広大なリージェント・パーク。多くの人たちがのんびり癒しの時を過ごしていた。動物園もある)
アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)②
- 2012-05-23 (Wed)
- 総合

共に手頃な値の下宿を探していたホームズとワトソンはベイカー・ストリートで同宿の身となる。ワトソンにとってホームズは興味津々の男に映る。何しろ、ホームズは博学と無知が同居しているような不思議な人物だったからだ。His ignorance was as remarkable as his knowledge. と述べられている。ホームズが太陽系のことを全然知らないことにワトソンは驚愕を隠せない。「この19世紀に地球が太陽の周りを回っていることを知らない人間がいるとは」と。
そのワトソンに向かい、ホームズは平然と語りかける。無駄な情報・知識を自分の脳内に詰め込まないことが大切なのだ。人間の脳の「許容量」には限りがある。無駄を詰め込むと、本当に大切な情報・知識を収容するスペースが減ってしまうという主張だ。
“You see,” he explained, “I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things so that he has a difficulty in laying his hands upon it. … It is a mistake to think that that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.” (「分かるかい?」とホームズは説明した。「私は人間の脳はもともと荷物の入っていない小さな屋根裏部屋のようなものだと考えている。要は好きなように家具を入れていけばいいんだよ。愚か者は手に入るあらゆるがらくたを詰め込んでいく。彼にとって有益な知識はどこに入れたか分からないようになってしまう。それを探そうにも役立たない知識であふれ返っており、収拾がつかない。・・・その小さな部屋は弾力性があり、どこまでも膨らむことができると思うのは間違いだ。君が新しい知識を一つ獲得する度にそれまで蓄えていたものを一つ失うようになる時がやって来ることを覚えておくことだ。だから、役に立たない事柄を頭に入れることで有益な知識が失われることのないようにすることが最重要なことなんだよ」)
昨今のテレビではやる「豆知識」や「雑学」を売りにしたクイズ番組、たいして芸のないお笑い芸人が跋扈(ばっこ)するバラエティ情報番組の「氾濫」に多少辟易している私としては、上記の主張には諸手を挙げて賛成したい。
例えば、「夏目漱石」という作家の名前の読み方や、彼の作品に「吾輩は猫である」とか「坊っちゃん」「こころ」という作品群があることを知っているだけでは雑学の域を出ないだろう。そうした作品を読んで味わって初めて意味がある。昨今のクイズ番組は単に雑学的知識を競い、あおっているだけのような気がしてならない。大人はまだいい。多感な子供たちが悪影響を受けなければいいがと思う次第だ。余計なお世話かもしれないが。
(写真は、ロンドンで買った“A Study in Scarlet” 。価格は6.99ポンド[約980円])
アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)①
- 2012-05-22 (Tue)
- 総合
ロンドンに着いて最初に足を運んだ観光名所はシャーロック・ホームズ博物館だ。有名人の蝋人形館で知られるマダム・タッソーにも近い。ホームズものに登場するベイカー・ストリート221b番地にある民家をそのまま活用した博物館は1990年にオープンしている。入場料大人6ポンド(約840円)。二階の書斎にいた世話係りの女性は「今日はお客が少ない方です。多い時には通りに行列ができ、1時間待ちということもありますよ」と語った。

実を言うと、私はシャーロック・ホームズものを最近まで読んだことがなかった。英文学の旅なら、ホームズものは「必須」かなと思い、何気なく、手にしたのが、“The Adventures of Sherlock Holmes” 『シャーロック・ホームズの冒険』だった。いや、正確に書くと、私がアフリカの旅以来重宝している電子辞書に「世界文学100作品」という「棚」があり、この中にドイル卿の名著が収納されていた。
一番手に掲載されていたのが “A Study in Scarlet” 。『緋色の研究』という邦訳が定着しているようだ。『シャーロック・ホームズの冒険』シリーズの先駆けになった作品で、探偵ホームズとワトソン博士が知り合った経緯が冒頭に紹介されている。
この作品が書かれたのは1886年で翌87年に発表されている。ロンドンの街中をハンサム(hansom)と呼ばれる「2人乗り1頭立て2綸馬車」が石畳をきしらせながら走っていた時代であることが分かる。もっとも、19世紀末のこの時代に、ロンドンではすでに地下鉄(Underground) が走っていたことも記されている。世界で初めてここロンドンで地下鉄が通ったのは1863年とか。日本はまだ明治維新前だ。当時はロンドンが世界に冠たる大都市であったことは容易に想像できる。

私のように50歳代後半になって初めてホームズものを読むと、小説のプロットの他の部分に結構「目」がいってしまう。例えば、登場人物がお互いをどう呼び合っていたかということが気になった。私の記憶ではお互いをファミリーネーム(名字)で呼び合っており、ファーストネームで語りかける場面は見られなかったように思う。それも、敬称なしのファミリーネームだ。ホームズはワトソン博士のことを第三者がいる時には “Dr. Watson” と呼んでいたが、二人だけの会話の時には単に “Watson” と呼んでいた。ワトソンも “Holmes” と応じている。当時は今と異なり、あまりお互いをファーストネームで呼び合う習慣はなかったのだろうか。
小説はIn the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London,…という書き出しで始まる。語り手はワトソン博士だ。ワトソンは大学卒業後、軍医としての訓練を経て、副軍医としてインド駐屯の軍に勤務を命じられるが、彼がボンベイ(現ムンバイ)に到着した時、第二アフガニスタン戦争が勃発、自分の軍は敵陣深く入っており、急いでカンダハルに向かったことが述べられている。1878年のことであるが、現在米軍やNATO(北大西洋条約機構)軍が撤退を模索している、戦火のやまないアフガニスタンの情勢が一瞬脳裏に浮かび、奇妙な印象を禁じえなかった。
(写真は上から、シャーロック・ホームズ博物館の外観。実際にドイル卿が下宿していた民家でないが、ドイル卿や探偵ホームズの作品のゆかりの品々が数多く展示されていた)
ダイヤモンド・ジュビリーへ
- 2012-05-18 (Fri)
- 総合
ロンドンに到着してほぼ一週間。文学紀行的な文章を早く書いてみたいのだが、毎日郊外の宿からバスと地下鉄を乗り継いで中心部まで出かけているので、帰宅すると結構疲れている。読みかけの本もあってそっちの方も気になる。かてて加えて、書店をのぞいていたら、面白そうな本を見つけ、これも買ってしまった。「遅読」の私にはますます辛い。

ロンドン中心部の目抜き通り、オックスフォードストリートにはエリザベス女王の即位60周年を意味する「ダイヤモンド・ジュビリー」(Diamond Jubilee)を祝うユニオンジャックの垂れ幕が掲げられ、華やかな雰囲気だ。6月3日にはテムズ川で豪華な記念行事が催される運びという。1000隻以上の船に、女王以下英王室のメンバーを含め2万人の参加者が集い、河畔から100万人の人々が見守るこの催しを、地元紙は "world’s biggest outdoor party" と表現していた。
7月末からはご承知の通り、ロンドン五輪が開催される。それで、英国中が二つの大イベントを前に盛り上がっているかと思っていたが、正直言って、よく分からない。盛り上がっているようでもあるし、そうでもないようである。今は、祝賀ムードに浸るよりも、ギリシャがユーロ圏から抜けそうな危機的状況に関心が行くのは仕方ないにしても。
カフェで目の前に座った私より少し年配の女性二人に話しかけてみた。ロンドンの南にあるギルドフォードという町に住んでいる姉妹のおばさんたちだった。「そりゃあ、楽しみにしていますよ。6月3日には私たちが住んでいる地区でもストリートパーティーがあります。オリンピックも楽しみ。聖火リレーはギルドフォードを通りますし」とほほ笑んだ。「オリンピックで景気も少しは良くなるんじゃないかしらと期待もしていますわ」

木曜日のガーディアン紙では、五輪開催により、GDP(国内総生産)を0.2ポイント押し上げるではという英国銀行の試算が報じられていた。五輪を見に来る海外からの観光客が落とすお金や五輪関連の公共工事などによる景気拡大を見越しての試算のようだ。もっとも、過去50年の例で見ると、五輪を開催した国は五輪後に必ず景気後退があり、永続的な効果は期待できないという経済専門家の見方も紹介していた。
ロンドン五輪が地元の人々、特に仕事を探している若者にとって、貴重な就業の機会を与えることは間違いないようである。木曜日のイーブニング・スタンダード紙(無料紙)は、ケータリング(仕出し業)や警備関係、清掃作業などの分野で少なくとも1万2千人のロンドンっ子が五輪期間に働く機会を手にすると報じていた。五輪期間中に雇用される人々の総数は約20万人に上る。五輪がもたらす臨時雇用の場が失業中の若者にとって長期的に仕事を見つける機会になることも期待されるという。
さまざまな期待を込めて、聖火リレーはこの土曜日、イングランド南西端のランズエンドからスタートし、12歳から100歳の市民8000人がリレーして、北アイルランドを含む英国全土を走り抜け、7月27日、ロンドンのオリンピックスタジアムに運ばれる。テロや混乱なく、ロンドン五輪が開催されることを切に願う。
(写真は上が、英国国旗のユニオンジャックが飾られた目抜き通りのオックスフォードストリート。下が、「あなたが女王様でも手にしておかしくないバッグ」と宣伝している商店)
一般紙もタブロイド版
- 2012-05-17 (Thu)
- 総合

毎朝起きて、近所の雑貨店のようなお店に行き、朝刊各紙を買い求める。「悲しいさが」か、朝起きると何であれ新聞を目にしたい。英国では今やブロードシートではなくて、タブロイド判の新聞が目立つ。タイムズもインディペンデントもタブロイド判になっている。バスや電車の中で読むときにはこちらの方が読みやすい。(現存する新聞では世界最古の歴史のタイムズは日本語表記の上では確かザ・タイムズとザを付けるべきだったか)
こちらに来て、旧知のイギリス人女性に、今の英国でどの新聞がベストの新聞だろうかと尋ねたら、即座に「ガーディアン」という答えが返ってきた。彼女は保守的思考をする人ではないので、そうだろうなとは思っていたが。(参考までにガーディアンとインディペンデントはともに1.20£[168円]、ザ・タイムズは1ポンド)

久しぶりに朝刊各紙を見て思ったのは、いや、こうした新聞をつぶさに読んでいたら、日が暮れてしまうという思いだ。新聞社のロンドン支局勤務時代にしてそうだった。毎朝朝刊各紙に目を通し、日本に転電して然るべきニュースがあれば、適宜翻訳して送稿する。送稿後に個人的に興味を覚えた記事をゆっくり読むのだが、ネイティブでない身には相当骨が折れた。英紙は米紙のニューヨークタイムズほどではないにしても、日本の記事に比べれば、総じて長い。できるだけ沢山の情報が詰め込まれている印象だ。
本日水曜日の紙面を見ると、廃刊に追い込まれたタブロイド紙の盗聴疑惑事件の裁判のニュースが大きく報じられていた。そのタブロイド紙で敏腕を振るっていた女性元編集長らが司法妨害の罪で起訴されたからだ。女性元編集長は「起訴は大間違い。税金の無駄遣い」と怒り心頭だった。ギリシャの政局の混乱、それを受けて、就任したばかりのフランスのオランド新大統領がドイツのメルケル首相と欧州連合の危機打開に向け、初めて会談したことも大きく報じられていた。
私がここで勤務していた時に欧州連合の足並みを乱す最大の懸念はボスニア紛争だった。民主主義と人権を掲げる欧州連合の足元で、ボスニアのムスリム人がかつての同胞のセルビア人から「民族浄化」の名のもとに虐殺されていた。寝起きに聞いたBBCラジオでは、民族浄化を陣頭指揮していた悪名高いムラジッチ元司令官がオランダ・ハーグの国連旧ユーゴ国際法廷にこの日出廷するという。こちらはいい意味での「諸行無常」だ。

活字メディアに関してもう一点。地下鉄の駅などでいわゆるフリーペーパーが配られているが、これも読んでみると、一般の有料紙とそう遜色ないほど読み応えがある。私がロンドン支局勤務に勤務していた90年代はフリーペーパーが出始めたころだったかと思うが、読んだ記憶は残っていない。
有料紙の記者に折をみて話を聞きたいと思っているが、ネット社会の発展を合わせ考えると、既存の活字メディアが生き抜いていくのは日本のみならずここでも大変だろうと推察された。
(写真は上から、ガーディアンやインディペンデントなどの英各紙。バスや地下鉄などの座席に捨て置かれていることの多いフリーペーパー。大衆紙のサンの売りとも言える、3頁目にある若い女性のピンナップ写真も「健在」だ)
天候が一転
- 2012-05-15 (Tue)
- 総合
「これ以上のすがすがしさを望んだら、罰が当たりそうだ」と書いたばかりだが、いや、週明けは天候が一変、雨模様となった。しかも、寒い。週末はポロシャツで十分だったが、上着がいる。上着は秋を見越して厚手のジャンバーを一着だけトランクに詰めていた。少しでも軽く旅をしたいので、最後まで持参するか迷った一着だったが、よくぞ持ってきたと思う。これがなければ、肌寒い思いをしたことは間違いない。
毎朝起きると、枕元に置いている携帯ラジオのスィッチを入れる。FMでBBC(英国放送協会)のRadio4を聞く。特派員時代も毎朝欠かさず耳を傾けたニュース放送だ。定時のワールドニュースに続き、世界中の時の話題が流れてくる。報道の質の高さは昔も今もさすがだ。私は個人的にBBCこそ世界で最も優れた報道機関だと思っている。昨年アメリカの田舎を旅している時もBBCニュースが地元のFM放送で聞けることがあったが、ありがたく拝聴した。
出国に際し、現地通貨のポンドをある程度、東京・銀座にある都銀推奨の両替商で入手していた。ロンドンの中心部を歩いてそこかしこにある両替店に入り、レートを比較して見る。1ポンドを手にするのに何円必要かということだ。銀座の両替商では1ポンド=約140円のレートだった。こちらではお店によって差があるが、私が見た限りでは1ポンドが142円から148円という感じだった。14万2千円向こうに渡せば、1000ポンドくれるという勘定だ。しまった、これなら、もっと出国前に両替しておくのだったと少し後悔。

140円を切るお店がないかと歩いていたら、あった。昔住んでいて、土地勘が多少なりとも残っていたトッテナムコート通りのお店で交渉したら、約133円で両替してあげると言う。まあ、大枚を両替するわけではないので、一喜一憂する差額ではないのだが、それでもちょこっと嬉しい。よく覚えていないが、この国に赴任した1993年の手帳を見ると、成田空港で12万3840円を720ポンドに両替したと記している。1ポンド=172円のレートだ。トッテナムコート通りのお店なら、931ポンドになる。200ポンド以上も多い。(このブログでは日本円への換算は上記の1ポンド=140円で計算)
ロンドンの中心部を歩いていて、気づくのは日本食レストランが格段に増えたことだ。もっとも経営者や厨房にいるのは日本人ではなく、韓国人や中国人であることがしばしばだが。プラスチック容器に見栄え良くスシを並べ、味噌汁はサービスしているファーストフード的なお店もあった。味は今一で、あえてまた足を運ぶ気には到底ならない。
ロンドンと言えば世界に名高い「イングリッシュブレックファースト」。これを食さないわけにはいかないが、ちょっとしたレストランやカフェでは少なくとも8ポンド以上はする感じだ。これにイングリッシュティーを追加すれば、10ポンド(1400円)程度の値段となる。ひところ、630円の納豆定食(ウィンナーソーセージに卵焼き付き)が朝食の定番だった身には「高い!」と思わざるを得ない。愛着のあるイングリッシュブレックファーストについては後日また触れたい。
(写真は、比較的あっさりしたイングリッシュブレックファースト。ティーを2杯飲んで約8ポンド[1120円]だった。ロンドンは総じて高い、いや、高すぎる!)
ロンドンの賑わい
- 2012-05-14 (Mon)
- 総合
久しぶりのロンドン。覚えていることも多々あるが、忘れてしまっていることも少なくない。早く心身ともに「英国モード」にするしかないようだ。まずは時差の克服。若い時にはすぐに切り替えることができたような気がするが、この年になると完全に地元の時間帯に慣れるには1週間程度かかる。少なくとも私にはそうだ。日曜の今朝も3時ごろ目が覚め、その後もうつらうつら状態が続いた。これに「五十肩」のうずきが追い打ちをかけるから、何とも情けない。

土曜、日曜とロンドンの繁華街を歩いた。相変わらず、観光客で賑わっている。ニューヨークといい勝負だろうか。デジカメを手に至るところで写真を撮りまくっている。ヨーロッパからの観光客も少なくないと思われる。英国やロンドンにしてもヨーロッパを今覆っている不況、閉塞感と無縁ではないだろうから、少し不思議な思いもする。
机の上に置いた温度計で毎日チェックしている気温は20度から21度。湿度は28%程度。これ以上のすがすがしさを望んだら、罰が当たりそうだ。英語で表現すれば、”I feel fresh and crisp.” とでも言うのだろうか。
毎朝5時ごろには外が明るくなっている感じだ。もっと早い時刻かもしれない。夜は9時を過ぎても仄明りが残っていて、夜道を歩く感覚ではない。サマータイムのシーズンであり、時計の針を1時間早めているにしても、この明るさは久しぶりに体験すると戸惑ってしまう。
今寝起きしている場所はホテルではない。少しでも「節約旅行」にするため、つてを頼って、郊外の民家の屋根裏部屋に住まわせてもらっている。土曜日には玄関の鍵を部屋に置き忘れて出かけてしまった。夕刻6時ごろに帰宅してみたものの、この住宅の他の部屋に住んでいる人(確か2人いたような)は当然のことながら、まだ帰宅しておらず、私は部屋に入ることができなかった。

「同居」の住人が誰か帰宅するまで時間をつぶすしかない。近くを少し歩くと、パブが一軒目に入った。丁度いい。簡単な食事もここで済ませよう。入ってみたら、アイリッシュパブで、怖そうなおばちゃんが「食事はない。うちはフットボール(サッカー)を見ながら、お酒(ビールやウイスキー)を飲むパブだ」とのたまう。ギネスを1パイント(約568cc)注文。そのうちに右隣にやってきた青年が「おや、わが国のビールを飲んでくれてありがとう」と話しかけてきた。パディと名乗った青年はアイルランド出身で35歳の左官。「パディ、私はギネスが好きなんだ。9月にはアイルランドを訪れたいと思っている」と応じる。気が付いたら、ギネスを5杯にウイスキーを少々飲んで(飲まされて)いた。私が支払ったのは最初のギネス2パイントだけ。
アイルランド人は人懐っこくて、とても親日的だ。パディと盛り上がった話の話題はアイルランドとイングランドの微妙な関係だが、それは後日、改めて触れたい。
(写真上は、ロンドンの地下鉄は世界最古の歴史を誇る。従って対面の乗客のひざが間近に迫る狭い空間だ。下は、中心部のピカデリーサーカス。観光客でいつもの賑わいを見せていた)
はじめに
- 2012-05-10 (Thu)
- 総合
アメリカの旅から帰国して早くも4か月が過ぎた。いよいよ、当面最後の海外の旅に出る時が来たようだ。今度は英国。1990年代半ばに3年間、新聞社の特派員勤務をしていたロンドン再訪となる。時間の余裕があれば、お隣のアイルランドも訪ねたいと考えている。
アメリカの旅同様、文学の香りを求めた旅になればと願っている。大学ではサマセット・モームの文学を卒論のテーマにした経緯がある。特派員勤務時代には残念ながら、モームゆかりの地を訪ねる機会はなかった。あのシェイクスピアゆかりの地、ストラトフォード・オン・エーヴォンにも足を運んだことがない。仕事一筋だったからでは無論ないが、それでも新聞社勤務だとそう気楽に文学散歩にいそしむゆとりがなかったことも事実だ。
早期退職後、アフリカ、アメリカと取材の旅を続けてきた身。エネルギーとは「ものの勢い」とどこかで読んだか耳にした記憶がある。それなら、浅学非才、手元不如意の身なれど、「走りながら考える」いや正確には「走りながら考えている振りをする」エネルギーだけはある。それが衰える前に旅立たなくてはという心境だ。
アメリカ同様、行き当たりばったりの旅。このメールを書いている10日午後、まだ、最初の訪問地となるロンドンのホテルさえ決めて(決まって)ない状況。明日11日早朝、今投宿している浅草千束のホテルを出て成田空港に向かうまでには、ネットで安宿を探したいと思っている。
さて、どんな旅になるやら。ロンドンについて言えば、特派員勤務後、確か二度ほど足を運んだことがあるが、いずれも駆け足での訪問だった。実質的には16年ぶりの長期滞在だ。懐かしい友人、知人との再会とも楽しみ。イングランドの食文化も久しぶりに味わってみたい。気がかりなのはこちらの体調が万全でないこと。病を患っているわけではない。昨年暮れから左腕の上腕部が痛んでいる。日中はいいのだが、寝ている時、未明にうずいて目が覚めることがしばしば。激痛ではないから、寝相を変えて何とか眠ろうとしているが、睡眠が浅くなるのは致し方ない。それで大好きなゴルフもずっと遠ざかっている。
お医者さんに診てもらったら、「肩関節周囲炎」と診断された。どうやら「五十肩」の一種らしい。ちなみに「五十肩」は英語では fifty shoulders というらしい。いや、これは冗談。和英辞書を引くと a frozen shoulderと出ている。なるほど、左の肩甲骨の辺りが強張った感じが良く出ている。願わくは、この旅を続けている間に左腕の痛みが自然に治癒して、イングランドやスコットランドのヒースを舞台にしたゴルフ場で元気にドライバーを振り回す日のあらんことを。
◇
今回の旅は約5か月の予定です。時々のぞいていただければ幸甚です。別にオリンピック見たさに行くわけではありませんので、誤解なきよう。いや、足を運んだ先で何かオリンピックの競技が行われていれば話は別ですが・・・。







